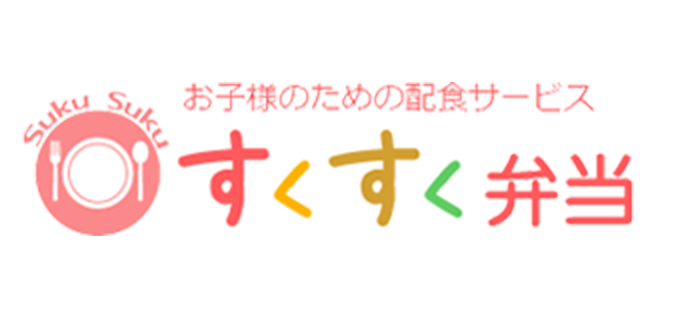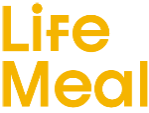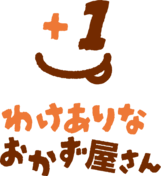こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!

春は、花粉や大気汚染などによってさまざまなアレルギーが出やすい時期ですね。目に見える不調とまではいかなくても、何となく目がかゆかったり、鼻が詰まっていたりすることもあります。鼻詰まりは呼吸がしにくくなり、食事がのどを通りにくくなる原因の一つにもなります。
今回は、主に花粉症の症状を緩和する効果があるといわれる食材とそのレシピをご紹介します。
目次
季節の養生:花粉症とは?
花粉(抗原)が体内に入ることにより発生するアレルギー症状
花粉症とは、風に乗って空中を浮遊している花粉が、目の粘膜に付着したり呼吸により肺や気管支に入ってしまったりすることによって発生するアレルギー反応のことを言います。
目の粘膜や呼吸器に花粉が付着すると、私たちの身体はその花粉が敵なのか味方なのかを判断します。
アレルギーを持つ方は、この花粉を「敵」と認識しているのですね。そのため、体内に抗体が作られ、ヒスタミンなどのアレルギー誘発物質が放出されます。この物質の刺激で、いち早く花粉を除去するためにくしゃみや鼻水、また、目のかゆみを引き起こしているのです。
実は一年を通して花粉症は発生している
日本では春に発生するスギやヒノキの花粉症患者が多く、毎年の花粉飛散量予測もニュースで大きく取り上げられていますが、実は一年を通してアレルギーを誘発する可能性のある植物の花粉が飛んでいます。ある一定の季節がくると何となく調子が悪い、という方は、花粉症が原因なのかもしれません。
血液検査で特定のアレルゲンを調べることもできますので、かかりつけの内科、アレルギー科を受診、相談してみるとよいですよ。
主な花粉の種類と飛散時期は下記の通りとなります。
| 季節 | 花粉の種類 |
|---|---|
| 春 | ハンノキ・スギ・ヒノキ |
| 夏 | シラカンバ・イネ |
| 秋 | ブタクサ・ヨモギ・カナムグラ |
| 冬 | スギ |
花粉症が原因の食物アレルギーもある
また、単なる花粉症、と思っていても、花粉症が原因で思わぬ食物アレルギーを誘発することがあります。口腔アレルギーといい、花粉と似たアレルゲンの構造をしたものに体が誤って反応することで発症し、唇や口の中、喉の腫れ、かゆみやイガイガ感が現れます。ひどくなると目や鼻の粘膜の充血、呼吸困難や、まれに血圧の低下、アナフィラキシーショックを起こすこともあります。
すべての人に必ず当てはまるわけではありませんが、食後に不快な症状が現れた時は関連性を疑ってみるとよいですね。
特定の花粉と食物の関連性が確認されているものもありますので、参考までにいくつかご紹介します。
| 花粉 | 関連の認められている主な食べ物 |
|---|---|
| ハンノキ属 | リンゴ、イチゴ、モモ、サクランボ、メロン、スイカ、キュウリ、ニンジン、セロリ、キウイ、オレンジ、ゴボウ、大豆など |
| シラカンバ | リンゴ、モモ、ナシ、洋なし、スモモ、アンズ、にんじん、セロリ、オレンジ、メロンなど |
| スギ・ヒノキ | トマト |
| ブタクサ | スイカ、メロン、キュウリ、バナナなど |
| ヨモギ | ニンジン、セロリ、レタス、ピーナッツ、クリ、ジャガイモ、トマトなど |
アレルギー症状の出方に合う食材
サラサラとした鼻水が止まらなくなるとき

サラサラとした鼻水がとめどなく出る時は体が冷えてしまっていることがあります。
体を温めつつ、アレルギーによる炎症を抑える働きがあるレンコンを使った料理がおすすめです。
花粉症ではなくとも、秋口の冷えや風邪の初期症状が感じられるとき、熱に強いビタミンCを豊富に含み、肺を潤し咳を止める効果のあるレンコンの料理はぜひともメニューに上らせたいものです。
なお、とても薬効のあるレンコンですが、高温で加熱するとその効果も若干失われてしまいます。出来れば煮るか蒸す料理を選んでください。
海老には体を温め、食欲増進、体力の回復に効果があります。併せて使うとよいですね。
≪海老入りれんこん饅頭≫
【材料】
| れんこん | 100g |
|---|---|
| じゃがいも | 50g |
| 片栗粉 | 大さじ1/2~ |
| 塩 | ひとつまみ |
| 海老 | 100g |
| 酒 | 小さじ2 |
| 塩 | ひとつまみ |
| おろし生姜 | 1/2かけ |
| 片栗粉 | 小さじ1 |
| 出汁 | 300cc |
| しょうゆ、みりん、塩 | 各適宜 |
| 水溶き片栗粉 | 少々 |
| お好みで吸い口にゆずや木の芽など | 適宜 |
【作り方】
1. れんこん、じゃがいもはすり下ろし、キッチンペーパーを敷いたざるに入れ、余分な水分を自然に落とすように切る。
2. 海老は殻とわたを取り、塩をふって包丁で叩いて粘りを出す。
3. (2)におろし生姜、酒、片栗粉を加えさらによく混ぜ、4個に分けて団子状に丸める。
4. (1)のれんこんとじゃがいもに塩、片栗粉を加え混ぜる。生地が団子状に丸められる程度に片栗粉を足していき、まとまるようになれば4個に分け、(3)の海老団子を包む。
5. 湯気の上がった蒸し器で蒸すか、ラップに包み、電子レンジ600Wで5分程度加熱し、中の海老までしっかりと火を通す。
6. 出汁を温め、1.で切った水分を加える。しょうゆ、みりん、塩で味を整え、ひと煮立ちさせる。レンコンやジャガイモのでんぷんでとろみがつきますが、足りないようなら水溶き片栗粉でとろみをつけて(5)の団子にかけ、吸い口に香りのよいゆずや木の芽を添える。
※咀嚼、嚥下に不安がある場合※
れんこんをすり下ろし、出汁に直接加え、そのまま煮立たせて味を整え、すり流しにします。れんこんには多くのでんぷん質が含まれるため、とろみもしっかりと付きます。
なお、れんこん饅頭として食べる場合、片栗粉を入れすぎると固く弾力が出すぎて食べにくくなります。使用量は控えめにし、まとまりにくいときは水分を切りましょう。絞った汁のなかにはアレルギーを抑える成分が多く含まれます。出汁の方に加え、残さずいただきましょう。
頭がぼーっと熱く、頭痛があり鼻が詰まっているとき
このような症状の時は体内に余分な水分や熱がこもってしまっています。
体の熱を取り、むくみを解消するには、カリウムの多い夏野菜が一番良いのですが、代謝の落ちている高齢者は、春に食べると体が冷え過ぎてしまう可能性もあります。
春におすすめなのが、旬を迎えるアサリや、ソラマメなどの旬の豆類です。アサリには穏やかに体の熱を取ると共に、むくんで溜まってしまった過剰な水分を体外に排泄する働きがあります。
ソラマメやスナップえんどうなど、春においしい豆類は消化器系の働きを助け、むくみを取り、体を冷やしすぎることもありません。
消化器系の働きを助ける力のある発酵食品の中から味噌を使い、ぬたはいかがでしょうか?
≪あさりとソラマメのぬた≫
【材料】2人分
| あさり | 14粒(缶詰でもよい) |
|---|---|
| 酒 | 50cc |
| ソラマメ | 6莢程度 |
| 白味噌 | 大さじ2 (白味噌が手に入らなければ田舎味噌などお好みのもので) |
| みりん | 大さじ1 |
| 砂糖 | 大さじ1(お好みで、味噌の甘さで調整して下さい) |
| 酢 | 大さじ1 |
【作り方】
1. あさりは砂抜きし、殻を優しくこすり合わせて洗い、酒蒸しにして身を取り出す。
2. ソラマメは莢からとりだし、塩少々(分量外)を入れた熱湯でゆで、薄皮をむいておく。
3. 味噌と砂糖を合わせて練り、酢、みりんを少しずつ加えながら溶きのばす。
(ここで練り辛子少々を加えるとからし酢味噌になりますが、熱がこもっているときは控えた方が良いです)
4.(1)、(2)をボールに合わせ、(3)の酢味噌を加えて和える。
※咀嚼、嚥下に不安がある場合※
ソラマメはやわらかく茹でてペースト状にします。あさりは蒸し汁少々(塩分が強すぎるようなら水で代用)を加えて刻むかミキサーにかけます。
目のかゆみがあるとき
目がたまらなく痒くなってしまったとき、有効なのが菊花茶やミントティーなどです。菊花は首から上の不調に良く、特に疲れ目の解消に効果があります。アレルギーを抑え、体の熱を取ってくれる黒きくらげやトマトを使った中華風サラダ、さらには目の充血を取り、デトックス効果もある菜の花のお浸しもおすすめです。
黒きくらげはスーパーの中華食材コーナーで乾物が、まれに生のものが野菜コーナー(きのこ類)に置かれていることがあります。
≪黒きくらげと豆腐の中華風サラダ≫
【材料】 2人分
| 黒きくらげ (乾燥品なら1g程度) | 2~3枚 |
|---|---|
| 豆腐 | 1/2丁 |
| セロリ | 少々 |
| スプラウト(またはカイワレ大根など) | 1/2パック |
| トマト | 中1個 |
| 酢 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| ゴマ油 | 小さじ2 |
【作り方】
1. 黒きくらげは乾物の場合は水につけて柔らかく戻し、石付きを取る。さっと茹でて千切りにする。
2. スプラウト(カイワレ大根)は洗っておく。長ければ一口大に切る。セロリはすじを取り、みじん切りにする。
3. トマトはくし切りにする。
4. 酢、しょうゆ、ゴマ油を混ぜ、ドレッシングを作る。
5. 豆腐を一口大に切り、器に盛り、黒きくらげ、アルファルファ、セロリ、を盛りつけ、ドレッシングをかける。
※咀嚼、嚥下に不安がある場合※
1.黒きくらげは柔らかく戻し、石付きを取り、やわらかく茹でる。時間をかけて茹でると、とろとろになります。
2.スプラウトは解毒、抗酸化・抗炎症作用が高く、中医学では目と関係の深い肝臓の働きを高めるといわれている野菜で是非とも取り入れたいものですが、意外に繊維が固いです。口に残ったり誤嚥を起こす可能性がありますので、心配な場合は細かく切ったものをミキサーにかけ、ゼラチンなどで固めると食べやすくなります。
3.トマトは種の粒が気になる場合があります。状況によって取り除いてください。セロリは堅いようならすりおろします。
4.ドレッシングがサラサラとして食べにくい場合、ゼラチンや市販のとろみ剤でとろみをつけてください。また、酢が強くむせてしまう可能性がある場合は、酢の量を減らすか、少量の砂糖やみりんを入れるとマイルドになります。
肌荒れがひどくなったとき
とめどなく出てくる鼻水を拭いすぎたり、目がかゆくて我慢できずに掻いたりして肌が赤く荒れている時は、美肌作りに効果的なハトムギがおすすめです。ハトムギには体の熱を取るとともにむくみの解消や食欲不振にも効果的です。
ただし、粒のままのものは硬く食べにくいので、豆を炊く時のように水に数時間ひたしておいてから炊いて食べましょう。最近は大きなスーパーマーケットでハトムギパウダーを販売していることがあります。揚げ物の衣作りに少し混ぜたり、つくねを作る際に片栗粉のように少し混ぜたりして使うのもよいですね。
≪はとむぎ粥≫
【材料】2人分
| 米 | 1/2合 |
|---|---|
| はとむぎ | 大さじ1~2 |
| 水 | 4カップ |
| 塩 | 少々 |
【作り方】
1. はとむぎはさっと洗い、たっぷりの水に3時間程度漬けておく。
2. 米を洗い、水、はとむぎを加え、全体が柔らかくなるまで中~弱火で炊く。
3. 塩で味を整える。
季節の養生(花粉症対応)まとめ
一口に「花粉症」と言っても、その症状によって向いている食材は様々ですね。薬膳では、花粉症とひとまとめにするのではなく、花粉を原因としてどのような症状があらわれているのかを考えて、合う食材、調理法を選びます。
今回ご紹介したもの以外にもたくさんの食材やレシピがありますので、いろいろとお好みにあわせたメニューで食べることを楽しみ、健やかな日々が過ごせるとよいですね。
 まごころ弁当
まごころ弁当  配食のふれ愛
配食のふれ愛  宅食ライフ
宅食ライフ  すくすく弁当
すくすく弁当  まごころケア食
まごころケア食  ライフミール
ライフミール  わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん  運営会社
運営会社  こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ