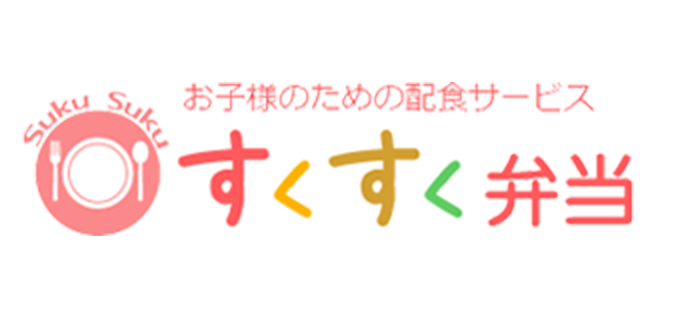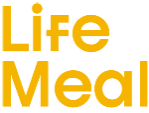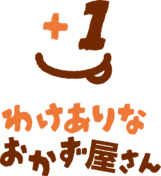こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!

日本人の死因の1位はがんであり、今や2人に1人ががんになる時代と言われています。
その中でも大腸がんの患者数は多く、1年間に10万人あたり103人が新たに大腸がんと診断されています。
大腸がんの患者数と死亡率は高齢化の進展と食の欧米化により年々増加傾向です。
ここでは、大腸がんや、大腸を切除した方向けの食事療法などについて解説していきます。
目次
大腸がんとは?
大腸は食べた物の水分を吸収し、便を作る臓器です。盲腸・結腸・直腸に分類され、これらに発生するがんを大腸がんといいます。
がんが進行すると次第に大腸の壁を浸潤し、やがては大腸の壁の外で散らばったり、リンパ液や血液の流れにのってリンパ節や肝臓、肺などに転移したりすることもあります。
早期の段階では自覚症状はなく、進行すると血便や下血、腹痛を引き起こします。
他にも貧血や、お腹が張ったり、腫瘍が原因で便が細くなったり便が残るような感じがすることもあります。
2015年度の人口動態統計によると大腸がんの部位別の発生率は、直腸が34.1%、結腸が65.9%です。
男性はおよそ11人に1人、女性はおよそ14人に1人が大腸がんと診断されています。
この20年で大腸がんによる死亡率は1.5倍に増加しており、高脂肪・低繊維食といった食の欧米化が関与していると考えられています。他にも飲酒や喫煙、運動不足といった生活習慣や肥満、家族歴も発生の要因に関与しています。
大腸がんの病期(ステージ)
| 0期 | がんが大腸の粘膜にとどまる |
| Ⅰ期 | がんが大腸の筋層にとどまる |
| Ⅱ期 | がんが大腸壁の筋層を超えているが、リンパ節転移はない |
| Ⅲ期 | がんがリンパ節に転移している |
| Ⅳ期 | 腹膜、肝臓、肺などへの遠隔転移がある |
大腸がんの治療法とは?
大腸がんの治療には、内視鏡治療、薬物療法、外科的手術、放射線治療などがあります。
治療法は、がんの進み具合や患者の全身状態や年齢などを考慮します。
がんの進行の程度が0~Ⅲ期では、がんが切除可能か判断し、可能であればがんを切除します。
切除する方法は、内視鏡治療と外科的手術があります。内視鏡治療は肛門から管をいれてカメラで腸内を見ながら大腸の内側からがんを切除する方法です。
外科的手術は、お腹を切ってがんが広がっている腸管や、がんが転移しているリンパ節を切除する開腹手術という方法と、へその周囲から細い内視鏡を腹腔内に挿入しがんが広がっている腸管を切除する腹腔鏡下手術という方法があります。
腹腔鏡下手術は傷が小さく、身体への負担が少ないので術後の回復が早いというメリットがあります。
どちらも、がんだけではなく大腸自体を切る必要があるため、術後大腸は少し短くなります。
食べた物の水分を吸収する機能のある大腸が短くなると、短くなった分水分を吸収できなくなるため便が柔らかくなったり下痢をしやすくなったりします。
また、食べたものを便として肛門へ送り出す大腸の動き(蠕動運動)が障害されることで便秘にもなりやすいです。
さらに、手術をすると傷を塞ごうとする正常な生体反応から癒着という粘膜同士や他の臓器とくっついてしまう状態にもなりやすく、大腸や小腸の癒着により食べたものが通りにくくなり、腸閉塞を起こすこともあります。
大腸を切除して繋ぎ合わせた部位が肛門に近い場合は、一時的な排泄口を腸の内側を折り返して体外に作ります。
これを人工肛門(ストーマ)といい、一時的な場合はおおよそ2~3か月程度で本来の肛門から排泄ができるように再度手術を行います。
しかし、がんが肛門の近くにあり肛門を残せない場合は永久的に人工肛門を造設しなければならないこともあります。
人工肛門について

人工肛門を保有している方は全国で18~20万人いると言われており、近年、人口の高齢化に伴い人工肛門を造設する手術を受ける患者も高齢化しています。
人工肛門があっても日常生活で制限されることは特にありません。慣れれば人工肛門をつけたまま外出や運動をしたり、旅行に行ったりすることもできます。
しかし、肛門には括約筋という筋肉があり自分の意思で便を我慢したり、出したりすることができますが、人工肛門では排泄のタイミングをコントロールすることができません。
そのため、袋状の装具をお腹に取り付け、便を受け止める必要があり、袋に便が溜まったら自分でトイレに捨てます。
最近では、人工肛門のある方が利用しやすいオストメイト対応トイレがある施設が増えてきています。
人工肛門から出てきた便は、取り付けた装具に溜まります。
装具は、皮膚保護材という直接肌に貼り付ける面(面板といいます)と、便を受け止める袋からなり、装具には防水や防臭効果があるため正しい付け方をしていれば便やにおいが漏れることはありません。
装具の交換間隔は一般的には週に2~3回程度で、発汗の程度や便の状態などにより個人差があります。交換日までは毎日同じ袋を使い、溜まったらその都度トイレに捨てます。
人工肛門の種類
人工肛門が造られる部位によって呼び方が違います。結腸に造られるのはコロストミー、回腸に造られるとイレオストミーと呼ばれます。
コロストミー:大腸から造られます。
上行結腸ではお腹の左側、横行結腸では上側、下行結腸やS状結腸では左側、と切除する部位によって造られる部位が異なります。
排泄される便も部位ごとに異なり、上行結腸では水っぽい便でS状結腸に近づくにつれ便は硬くなっていきます。
イレオストミー:小腸の回腸という部分の一部から造られます。
通常はお腹の右側に造られ、排泄される便は水っぽく、下痢のような便です。
人工肛門は、人によって形や部位が異なり、排泄口が1つの場合と2つの場合があります。
単孔式:排泄口が1つで、便が排泄されます。
双孔式:便が排泄される排泄口と粘液が排泄される排泄口の2つがあります。造られる場所により縦や横に並んでいます。
大腸がんの再発リスクを減らすには?
大腸がんの再発率はステージによって異なりますが、平均では17%です。再発を早期発見するためには、術後5年間は定期検査を受けるようにしましょう。
がんは、手術で完全にがんを取りきていても、目に見えないほどの小さながん細胞が体内に残っている可能性があり、この小さながん細胞が再発の原因となります。
大腸がんの再発をできる限り防ぐために術後に抗がん剤による治療を行うことがあり、これを「術後補助化学療法(アジュバント療法)」といいます。
術後補助化学療法は、リンパ節に転移があり再発の可能性が高い病期(ステージ)Ⅲの患者さんに推奨されます。
しかし、病期Ⅱの場合であっても再発の可能性が高いと医師が判断した場合には術後補助化学療法を行うことがあります。
一般的には手術後4~8週の間に治療を開始します。
術後化学療法では、1種類もしくは2種類の抗がん剤を使用して治療が行われます。
治療法にはいくつかの選択肢があり、がんの病期や効果と副作用のバランス、患者さんのライフスタイルなどを考慮して選択されます。
十分な再発予防効果を得るために通常6か月間の治療が推奨されています。
使用する薬剤は、内服薬のほかに静脈注射や持続点滴が必要なものがあります。現在では抗がん剤による治療は通院が一般的です。
手術でリザーバー(血管内に挿入するカテーテルと針を刺す台座から構成されます)を腕や鎖骨下の部分に埋め込むと、点滴が必要な時だけ携帯型ポンプから持続的に抗がん剤を注入することができるため、自宅でも持続点滴が可能となります。
抗がん剤の影響はがん細胞だけでなく、正常な細胞にも及ぶため副作用が起きることがあります。
副作用の症状や程度は使用する薬の種類によって異なり、個人差もあります。
近年では副作用を抑制したり予防したりする薬の開発も進んでいますが、強い副作用がみられる場合には、一時的に治療を休んだり減薬したりすることもあります。
大腸切除後の食事の注意点は?
大腸切除後にみられる症状の多くは完全に予防することは難しいものの、食事療法によって生じにくくすることは可能です。
大腸がんの術後は基本的に食事制限の必要はない、と言われていますが、術後生じうる不快な症状を少なくし、快適に生活するためには控えたほうがよい食べ物があります。
基本は栄養バランスの良い食事を、1日3食規則正しく食べることが大切です。
人工肛門を造設した場合も特に食事制限はありませんが、腸を切除しているため便秘や下痢など便の性状が不安定になりやすく、体調によっては食事の内容や調理方法を工夫する必要があります。
・食事は段階的に進め、一度にたくさん食べ過ぎない
手術をすると貧血などの症状が改善して手術前より食欲が増進することがあります。
食べ過ぎると下痢や腸閉塞を起こしやすくなるため、退院後は2ヶ月ほどかけて段階的に量を増やして、1回の食事量は腹8分目を目安とすると良いでしょう。
また、揚げ物や繊維の多い食品は少量ずつから食べ始めましょう。
・ゆっくりよく噛んで食べる
早く食べると腸に負担がかかり、軟便や下痢の原因となります。よく噛むと消化や吸収が良くなります。
・規則正しく食事をする
不規則な食事は便通を不安定にし、軟便や下痢、便秘の原因となります。
・食事はバランスよく、消化吸収しやすいものを中心に摂取する
消化の悪い食品を食べ過ぎると下痢や腸閉塞が起こりやすくなります。
消化しにくい食品は少量なら摂取しても問題ありませんが、よく噛むことや、細かくきざんだり、柔らかく煮込んだりなど食べ方や調理法を工夫することが大切です。
・食物繊維は患部が回復するまでは少し控える
食物繊維が多く、硬い食品(ごぼうやたけのこなど)は患部を刺激してしまいます。
十分に回復するまでは繊維質の食品は少なめにし、柔らかく煮るようにしましょう。
・アルコールはほどほどにする
アルコールは禁止ではありませんが、摂取することで食べ過ぎたり、下痢の原因となったりします。
また、炭酸を含むものだとお腹が張りやすくなるため、担当医と相談のうえで開始することをおすすめします。
アルコールは便のにおいを強くしてしまう原因にもなります。
大腸切除後の食品の選び方や調理法は?
術後3ヶ月程度は腸閉塞を引き起こす可能性があるため、消化の悪い食品や、食物繊維の多い食品は控えましょう。
また、お腹が張る原因となるガスが発生しやすい食品や、刺激が強い食品も控えめにした方が良いでしょう。
食材は細かくきざみ、煮る・蒸す・焼くなど調理法を工夫することで消化吸収を良くすることができます。
大腸手術後の食品の選択
| 食品群 | 消化の良いもの | 注意して食べるもの | 控えたほうが良いもの | |
| たんぱく質 | 肉類 | 鶏もも(皮なし) 鶏むね(皮なし) 鶏ささみ、鶏挽き肉、豚ヒレ 豚赤身、牛赤身、レバー | 鶏手羽 ロース肉、牛挽き肉 合い挽き肉 | 牛バラ、牛ロース 豚バラ、豚ロース カルビ、霜降り肉 加工品など |
| 魚類 | 白身魚(鯛、ヒラメ、カレイ 鱈、鮭)、サワラ、アジ、エビ 貝柱、ちりめん、練り製品 | 青身魚 干し魚 佃煮 | うなぎ、イカ、タコ ホタテ、刺身など | |
| 卵類 | 鶏卵、うずらの卵 | - | - | |
| 豆類 | 豆腐、高野豆腐、豆乳 引き割り納豆、こしあん | 納豆 おから(少量) よく煮た豆(少量) つぶあん(少量) きなこ(少量) 油揚げ(要油抜き) 厚揚げ(要油抜き」 | 硬い豆類(大豆、小豆など) | |
| 乳製品 | 牛乳、スキムミルク、チーズ類 ヨーグルト、乳酸飲料 | 生クリーム(少量)
| - | |
| 糖質 | 穀類 | 白米、お粥、食パン、うどん、マカロニ スパゲッティ(柔らかめ) | にゅうめん、春雨 ラーメン、菓子パン | 玄米、赤飯、雑穀米 チャーシューメン 日本そば、デニッシュ パイ、クロワッサン 揚げパン |
| 芋類 | じゃが芋、里芋、長芋 | さつまいも(少量) | こんにゃく | |
| 果物類 | りんご、桃、バナナ 缶詰の果物 | みかん、梨、キウイ すいか、メロン いちごなど | パイナップル、夏みかん 柿、干し柿 ドライフルーツなど | |
| 脂質 | 油脂 | 植物油、マーガリン バター、マヨネーズ | フライ(少量) 天ぷら(少量) 中華料理(少量) | 牛脂、豚脂 |
| ビタミン・ミネラル | 野菜 | 緑黄色野菜:かぼちゃ(皮なし) 人参、ほうれん草、小松菜 小ねぎ、トマト(皮なし)など 淡色野菜:大根、キャベツ、レタス、きゅうり、玉ねぎ なす(皮なし)、かぶ、白菜など | ピーマン アスパラガス | 硬い繊維の多い野菜 ごぼう、たけのこ れんこん、ふき、セロリ わらび、もやし、にら とうもろこし、切干大根 みょうが、漬物類など |
| 海藻類 | - | 海苔(少量) よく煮たわかめ(少量) | わかめ(酢の物など) 昆布、ひじき | |
| きのこ | - | - | きのこ全般 | |
| 嗜好品 | 飲料 お菓子 | プリン、ババロア、ゼリー 水ようかん、シャーベット ビスケット、カステラ 煎餅、麦茶、紅茶 | ケーキ(少量) 和菓子 濃い緑茶、ココア カフェオレ | 揚げ菓子、激辛菓子 アルコール類 ブラックコーヒーなど |
便通が変化したときはどうする?
(1)便秘
・術後3ヶ月以降であれば、野菜や果物など食物繊維を多く摂取する。
食物繊維が水分を吸収し便量が多くなり、便通改善効果があります。3ヶ月以内では腸閉塞の原因となるため注意しましょう。
・水分を多めに摂る
特に、起床時の1杯の水や牛乳が有効です。腸が刺激されて腸の動きが良くなります。水分摂取量は1日1,500ml以上を目標としましょう。
・食事時間を規則正しくする
特に朝食をしっかり食べることで腸を刺激します。また、朝に必ずトイレに入るようにすると、規則正しい排便の習慣を身につけることができます。
・適度な運動をする
身体を動かすことで腸の動きも活発になり、便通が良くなります。
開腹手術をした場合には、お腹に力を入れるような運動をすることで傷跡が大きく膨らんでくる腹壁瘢痕ヘルニアになるリスクが高くなるため、運動を制限する必要があります。
ただし、現在は腹腔鏡下手術が主流であり、運動を制限する必要はほとんどありません。
なお、食事や生活習慣に注意しても便秘が続く場合には主治医に相談しましょう。頑固な便秘には下剤が必要となる場合もあります。
(2)下痢
・消化の良い食品を摂る
下痢をしている時は腸を刺激しないこと大切です。消化が悪く刺激が強い食品は腸を刺激してしまうため避けましょう。
・冷たすぎず、熱すぎないものを摂る
温度が低すぎたり高すぎたりする食品は腸の動きを活発にするため、なるべく控えましょう。
・水分補給をしっかりする
下痢によって水分やナトリウム・カリウムなどの電解質が失われ脱水状態になりやすくなります。
ただの水よりも、電解質を補うことができるスポーツドリンクがおすすめです。
・少量ずつの食事をする
少量ずつ回数を増やすことで、消化管の負担を軽くすることができます。
※水分が摂取できない程体力を消耗し、脱水状態が疑われる時は速やかに医療機関を受診しましょう。
(3)頻便
大腸切除後、特に直腸を切除すると便を溜めることが難しくなり何度も便が出たり、便が直腸まで降りてきていないのに便がしたくなり何度もトイレに行きたくなる、ということがあります。
・手術後1年間は気長に様子をみる
→手術直後に不安定な腸の機能は身体の回復とともに徐々に回復してきます。
一般的に2~3ヶ月ほどで腸の機能は落ち着き、その後半年~1年かけて徐々に改善してくるため、焦らないで様子をみることも大切です。
・症状に合わせて、緩下剤や下痢止めなどの薬を使う
→術後1年以上経っている場合は劇的に症状が改善する見込みはあまりないため、主治医に相談し、薬でコントロールすることが必要になります。
(4)腹部膨満感(お腹の張り)
・ガスが溜まりやすい食品を避ける
→さつまいもなどの芋類、炭酸飲料やビールといったガスが溜まりやすい食品は避けましょう。ヨーグルトや乳酸飲料はガスの発生を抑える効果があります。
| ガスを発生させやすい食品 | 芋類、ごぼう、大根、貝類、豆類、ブロッコリー、炭酸飲料、お酒など |
| ガスの発生を抑える食品 | 乳酸菌飲料、ヨーグルトなど |
・1回の食事量を控える
→食事を控えても腹部膨満が続き、おならが出ない場合は腸閉塞が疑われるため、速やかに主治医に相談しましょう。
まとめ
大腸切除後の食事は、バランス良く規則正しい食生活を基本に、症状に合わせて食品の選び方や調理法を工夫することが大切です。
その日の体調や便の状態に合わせて、食品の選び方や調理法を工夫しましょう。
一方で、毎日の食事作りが負担に感じた時は配食サービスを利用してみても良いかもしれません。
高齢者向け配食サービス「まごころ弁当」には様々な種類のお弁当が用意されており、柔らかく消化吸収の良い食事が必要な方に向けて「やわらか食」というお弁当があります。
食材の見た目をそのままに柔らかく加工しているため、見た目にも美味しく食べることができます。
配食サービスは、買い物や調理する手間をはぶくだけでなく、不要不急の外出を避けることもできる今の時代に合ったサービスです。
安否確認も兼ねているので、遠方に住んでいるご家族の安心にも繋がります。
今なら2食まで無料で試食することができます。この機会にぜひお試しください。
 まごころ弁当
まごころ弁当 配食のふれ愛
配食のふれ愛 宅食ライフ
宅食ライフ すくすく弁当
すくすく弁当 まごころケア食
まごころケア食 ライフミール
ライフミール わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん 運営会社
運営会社 こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ