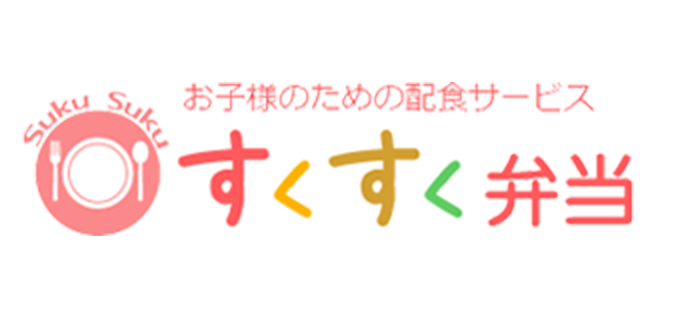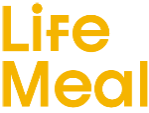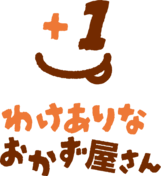こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!

「お酢は身体に良いのは分かっているけど酸味が強くて飲みにくい…」、そういった方におすすめなのがリンゴ酢です!
リンゴ酢は、リンゴの自然な甘みとフルーティーな風味でお酢の酸味が和らぐためお酢が苦手な人でも飲みやすく、ドレッシングやピクルスなどによく合うため料理にも使いやすい果実酢です。
また、リンゴ酢には、コレステロール値を下げたり、血糖値の上昇を抑えたりする効果があると言われています。
ここでは、リンゴ酢の効果や飲み方、血糖値を上げにくい食事の摂り方についても詳しく解説します!
目次
リンゴ酢の種類と効果
リンゴ酢とは、醸造酢1Lにつきリンゴの絞り汁の使用量が300g以上であるものを指します。
リンゴ酢には「純リンゴ酢」と「リンゴ酢」の2種類があり、醸造方法に違いがあります。
リンゴの搾り汁に酵母を加えて発酵させたアップルワインを種酢として、さらに酢酸菌を加えて発酵・熟成させたもののことを「純リンゴ酢」、リンゴの絞り汁に醸造アルコールを添加したものを「リンゴ酢」といいます。
リンゴ酢は純リンゴ酢よりも製造期間が短く安価で売られていることが特徴です。
純リンゴ酢は、リンゴ酢よりも高値ですが醸造酢にリンゴの絞り汁や果肉だけを加えて作られており、風味が豊で味わいが深いという特徴があります。
リンゴ酢が身体もたらす効果
リンゴ酢が身体にもたらす効果については様々な国で研究されています。
「1日1個のリンゴで医者いらず」ということわざがイギリスにある程、リンゴには体調を整えたり病気を予防したりする成分が含まれています。
一般的な穀物酢とリンゴ酢の栄養成分表を比較してみましょう。リンゴ酢には穀物酢よりも多くのナトリウム、カリウムが含まれていることが分かります。
特に、カリウムは穀物酢の約15倍もの量が含まれています。
<リンゴ酢の栄養成分表>
| リンゴ酢100gあたりの栄養成分 | |
| エネルギー | 41kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 2.4g |
| 食物繊維 | 0g |
| ナトリウム | 18mg |
| カリウム | 59mg |
| カルシウム | 4mg |
| マグネシウム | 4mg |
| リン | 6mg |
| 鉄 | 0.2mg |
| 亜鉛 | 0.1mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.1mg |
| ビタミンB6 | 0.01mg |
| ビタミンB12 | 0.3mg |
<穀物酢の栄養成分表>
| 穀物酢100gあたりの栄養成分 | |
| エネルギー | 37kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 2.4g |
| 食物繊維 | 0g |
| ナトリウム | 6mg |
| カリウム | 4mg |
| カルシウム | 2mg |
| マグネシウム | 1mg |
| リン | 2mg |
| 鉄 | ※Tr |
| 亜鉛 | 0.1mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.1mg |
| ビタミンB6 | 0.01mg |
| ビタミンB12 | 0.1mg |
※TrとはTraceの略で、成分が含まれてはいるが最小記載量に達しておらず、微量であることを示します。
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂):文部科学省 (mext.go.jp)
カリウムには、身体の中の余分な塩分(ナトリウム)を排出させ、高血圧やむくみを防ぐ効果があります。
また、リンゴに含まれるペクチンには、コレステロールの吸収を抑制しコレステロール値を下げる効果があります。
このペクチンによって糖分の吸収も抑制されるため血糖値の上昇がゆるやかになると言われています。
他にもペクチンには腸の働きを良くして便通を整える整腸効果など様々な効果があります。
さらに、リンゴには強い抗酸化力を持つリンゴポリフェノールが含まれています。
ストレスや紫外線などで増えすぎた活性酸素は脂質を酸化させて血液をどろどろにしたり、しみやしわなどの原因にもなります。
リンゴポリフェノールには活性酸素を除去する働きがあるため、血流を改善させたり、美白効果が期待できます。
また、お酢に含まれる酢酸が血糖値の上昇を緩やかにしたり、内臓脂肪を減少させるなどお酢単体でも十分身体に良いことが分かっており、リンゴとお酢で作られたリンゴ酢を毎日続けて摂ると以下の効果が期待できます。
・血糖値の上昇を抑制
リンゴ酢に含まれるペクチンと酢酸が糖分の吸収を抑制し血糖値が上がりにくくなります。
・美肌効果
クエン酸が肌の新陳代謝を促し、古くなった角質や不要になった老廃物を排出し新たな細胞に生まれ変わらせるターンオーバーをスムーズにするため、美白や美肌効果が期待できます。
・ダイエット効果
クエン酸が代謝を促して脂肪の燃焼を助け、アミノ酸が脂肪の分解を促進させます。
・高血圧予防、むくみの改善・予防
カリウムの利尿作用により、塩分とともに余分な水分を尿として排出させるため、血圧を下げたり、むくみを改善・予防する効果があります。
・骨粗しょう症予防
クエン酸にはカルシウムを吸収されやすい形に変える働きがあります。
・整腸効果
ペクチンが乳酸菌を増殖させて腸内の環境を整えます。また、ペクチンには便の容積を増やし腸の動きを良くする働きがあるため、便秘の改善に効果があります。
リンゴ酢の効果的な摂り方
リンゴ酢を飲むタイミングに決まりはありませんが、血糖値の上昇を抑えるには、1日1~2回、大さじ1杯(15ml)のリンゴ酢を食前に飲むと良いとされています。
ただし、お酢を空腹時にそのまま飲むと胃液の分泌が促進されることで胃が荒れてしまうため、必ず水や炭酸水などで5倍以上に割って飲むようにしましょう。
胃の粘膜を保護してくれる牛乳やヨーグルトなどの乳製品で割るのもおすすめです。特に胃潰瘍や胃酸過多などの持病がある場合は、飲み始める前に必ず主治医に相談してください。
また、リンゴ酢を飲むと胃液だけでなく唾液の分泌も促進されるため、食欲が増進してしまう作用があります。
せっかく血糖値を下げたいのに食べすぎてしまうのは逆効果です。食べすぎてしまう方は食事中や食後に飲むようにしましょう。
さらに、酢に含まれる酸には歯の表面のエナメル質が溶かすことがあります。そのため。リンゴ酢を飲んだ後は必ず歯を磨くようにしましょう。
但し、リンゴ酢を飲んですぐに歯を磨くと酸で歯を痛めてしまうため、リンゴ酢を飲んで30分以上経過してから歯を磨くようにすることが大切です。
リンゴ酢を選ぶ時は名称が「清涼飲料水」と記載されているものでなく、「リンゴ酢」や「食酢」と記載されている調味料に属するものがおすすめです。
また、アルコールを添加して作られたリンゴ酢より、リンゴの果汁を酵母で発酵させた純リンゴ酢のほうがリンゴ果汁の量が多いため血糖値の上昇を抑制する効果が期待できます。
リンゴ酢は醸造過程で濾過されていますが、大事な栄養成分も失われてしまいます。無濾過のリンゴ酢も売られているので、製造方法に注目して選んでみるのも良いでしょう。
~リンゴ酢を飲む時に注意するポイント~
・そのままではなく必ず水等で5倍以上に割って飲む
・食欲が増進されるため食べ過ぎないようにする
・適量を守り、飲み過ぎない
・リンゴ酢を飲んで30分以上経ってから歯を磨く
自家製リンゴ酢の作り方
市販のリンゴ酢の多くには糖分が含まれているため、飲み過ぎると健康を害するおそれがあります。そのため、リンゴ酢をジュースの代わりに飲むのはおすすめしません。
糖分が気になる方のために自家製リンゴ酢の作り方をご紹介します。ご自身のお好みで糖分控えめもしくは糖分を入れずに作ってみてください。
材料
お酢 200ml
リンゴ 1個
お好みで砂糖、はちみつなど
(1)リンゴ酢を詰める瓶は熱湯で消毒しておきます。
(2)リンゴを瓶に入る大きさに切り、瓶の中にお酢とリンゴを入れます。
(3)常温で保管し、1日1回はリンゴをひっくり返して混ぜます。
(4)1週間後に完成です。出来上がったリンゴ酢は冷蔵庫で保存します。飲む時にお好みで砂糖やはちみつを加えて甘さを調節しましょう。
使用するお酢は穀物酢だと独特のクセがあるため飲みにくいと感じることがあります。米酢や黒酢など様々な種類のお酢で作ることができるため、自分の好みに合うお酢で試してみてください。
保存料は使用していないため、保存期間は約3週間程度です。漬けているリンゴは腐敗してしまうため、2週間以内に取り出しましょう。
残った実はそのままだと酸味が強く食感も悪いのですが、ドレッシングに加えたり、砂糖とゼラチンでゼリーにすると残さず美味しく食べることができます。
リンゴ酢のアレンジレシピ
家族にもリンゴ酢を飲んで欲しい!そう思っても「お酢を飲む」と聞くだけで首を振る方も多いと思います。
そんな方におすすめなのが、普段の食事メニューの中にリンゴ酢を取り入れることです。
いつもの酢の物の代わりに使うだけでなく、メインの味付けをリンゴ酢に変えると塩分摂取量を減らすことにも繫がります。毎日の食事に取り入れやすいリンゴ酢を使ったレシピをご紹介します。
和風リンゴ酢ドレッシング
材料
リンゴ酢 大さじ2
醤油 大さじ1
ごま油 大さじ1
白いりごま 適量
ドレッシングはこれらの材料を混ぜるだけで完成です!作り置きしまうと酢と油が分離してしまうため、食べる直前に作ることをおすすめします。醤油ベースなので和食にぴったりのドレッシングです。
リンゴ酢と新玉ねぎのジャム
材料
新玉ねぎ 300g
リンゴ酢 80ml
(1)新玉ねぎを薄切りにして耐熱容器に入れます。
(2)リンゴ酢を加えます。
(3)ラップをして電子レンジ(500W)で12分温めます。
(4)粗熱が取れたら保存容器に移し、冷蔵庫で冷やします。
傷みやすい新玉ねぎをリンゴ酢と混ぜてジャムにすることで保存期間が延びるだけでなく、疲労回復や血栓予防など身体に嬉しい効果も期待できます。
冷蔵保存で3週間程保存可能です。納豆にそのまま混ぜたり、コンソメスープに加えたり、魚や肉に乗せて醤油を適量垂らして蒸し焼きにしたりなど、酢玉ねぎジャムを作り置きしておくだけで料理のレパートリーが広がります!
リンゴ酢ピクルス
材料
きゅうり 2本
パプリカ 1/2個 等お好みの野菜
リンゴ酢 200ml
塩 小さじ1
砂糖 大さじ1
ローリエ 1枚
粒胡椒 お好みで
(1)野菜は一口大に切ります。
(2)鍋にリンゴ酢、塩、砂糖、ローリエを加え煮立ったら火を止めて冷ましておきます。
(3)野菜は20秒程茹でて水を切り、粗熱を取ります。
(4)保存袋(容器)にピクルス液と下茹でした野菜を入れて軽くもみます。
(5)冷蔵庫で1日以上置いて完成です。
おつまみにもお弁当にもおすすめの一品です。
ピクルスに向いていない野菜はほとんど無いためお好みの野菜や冷蔵庫の余り野菜でもチャレンジしてみてください。
火を通す時間やピクルス液に漬ける時間を短くすると葉物野菜も漬けることができます。
手羽元のリンゴ酢煮(2~4人分)
材料
水 200ml
リンゴ酢 100ml
料理酒 60ml
ショウガ 10g
砂糖 大さじ2
醤油 大さじ2
みりん 大さじ2
うずらのたまご(水煮) お好みで
(1)ショウガを皮のまま薄切りにします。
(2)鍋にショウガ、手羽元、水、リンゴ酢、酒を加えてひと煮立ちさせます。
(3)砂糖、しょうゆ、みりんを加え、半開きになるように蓋をして30分弱火で煮込みます。うずらのたまごは煮込み途中で加えます。
お酢の力でお肉が柔らかくなるため、小さいお子さんからお年寄りの方まで食べやすくなります。手羽元だけでなく、鶏もも肉や豚肉などにもアレンジ可能です。
血糖値が上がりにくい食事方法
血糖値が高めで気になる方は、毎日リンゴ酢を飲むことに加え、食事の摂り方を工夫しましょう。
・1日3食規則正しく良く食べる
→欠食すると食事と食事の間隔が空いて血糖値が下がりすぎた状態になり、食事を摂った時に血糖値が急激に上がってしまいます。
また、欠食は一回の食事量も多くなりやすいため、3食規則正しく食べるようにしましょう。食事量は、朝3:昼4:夜3の比率にすると血糖値が上がりにくいとされています。
・寝る3時間前までに夕食を食べる
→就寝中はインスリンの働きが鈍くなってしまうため、寝る3時間前までに飲食は済ませるようにしましょう。
・ゆっくりよく噛んで食べる
→満腹中枢が刺激されるのは食事を始めて15分後と言われています。
そのため早食いは食べすぎの原因になります。食事量が抑えられればその分血糖値も上がりにくくなるため、できれば食事はゆっくりとよく噛んで30分以上かけるようにしましょう。
・GI値が低い食品を積極的に摂取する
食後血糖値が上昇する指標をGI値といい、GI値が低い食品は血糖値の上昇が遅くなりインスリンの分泌を抑えることができます。
肉や魚などはタンパク質が多い食品であり、GI値はそれほど高くありません。
GI値が高いのは米や麺などの炭水化物や砂糖などの食品で、これらを食べすぎないようにしてGI値が低い食品を食べるようにしましょう。
GI値が低い食品は腹持ちが良く、満腹感が持続しやすいとも言われています。
<食品のGI値>
穀物類
| 食品 | GI値 |
| フランスパン | 93 |
| 食パン | 91 |
| もち | 85 |
| 精白米 | 84 |
| 赤飯 | 77 |
| 胚芽精米 | 70 |
| スパゲッティ | 65 |
| そば | 59 |
| 玄米 | 58 |
| おかゆ | 57 |
| 全粒粉パン | 50 |
| 春雨 | 32 |
野菜類
| 食品 | GI値 |
| 人参 | 80 |
| かぼちゃ | 53 |
| ごぼう | 45 |
| 玉ねぎ | 30 |
| トマト | 30 |
| キャベツ | 26 |
| 大根 | 26 |
| アスパラ | 25 |
| ブロッコリー | 25 |
| きゅうり | 23 |
| レタス | 23 |
| もやし | 22 |
肉・魚類
| 食品 | GI値 |
| サバ | 40 |
| イワシ | 40 |
| 牛肉(バラ) | 45 |
| 鶏(ささみ) | 45 |
| 鶏(むね) | 45 |
| 鶏(もも) | 45 |
| 豚(バラ) | 45 |
| 豚(もも) | 45 |
| 豚(ロース) | 45 |
| 牛肉(もも) | 46 |
| 牛肉(ロース) | 46 |
| 塩鮭 | 47 |
出典:栄養学.net 食品のGI値一覧表
https://eiyougaku.net/gichiichiran/
・食物繊維の多いおかずから食べる
食物繊維には血糖値の上昇を抑える効果があります。
炭水化物は血糖値が上がりやすくなりますが、同じ量の炭水化物でも食物繊維を多く含んでいる方が血糖値は上がりにくくなります。
そのため、主食や主菜の前に野菜や海藻など食物繊維が多い食品から食べるようにしましょう。
根菜類や穀類など野菜によっては食物繊維を含んでいても糖質が多くGI値が高い食品もあるため注意が必要です。
リンゴ酢に関するまとめ
わが国の糖尿病有病者数は300万人以上であり、糖尿病予備軍はさらに多く潜んでいると推測されています。
血糖値が高めで気になる方は、リンゴ酢を飲む習慣を始めてみてはいかがでしょうか。
リンゴ酢は、毎日継続して飲むことが大切であるため、飲みやすさや続けやすい価格などを考慮して選びましょう。
リンゴ酢だけでなく、食事の摂り方にも気を付けるとより効果的に血糖値の上昇を抑えることができます。
健康な身体は毎日の食事が支えています。
高齢者向け配食サービス「配食のふれ愛」では、栄養士が考えた栄養バランスの良い食事をご自宅へお届けしています。
カロリー調整が必要な方のためのお弁当など様々な種類のお弁当があり、今なら無料試食サービスで2食まで試すことができます。この機会に是非お試しください。
 まごころ弁当
まごころ弁当  配食のふれ愛
配食のふれ愛  宅食ライフ
宅食ライフ  すくすく弁当
すくすく弁当  まごころケア食
まごころケア食  ライフミール
ライフミール  わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん  運営会社
運営会社  こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ