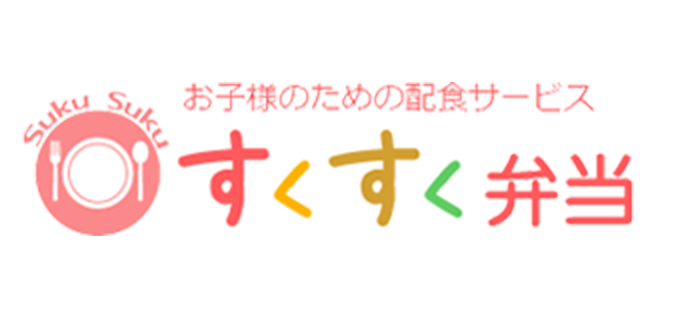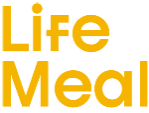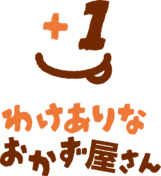こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!

年齢を重ねても安心して暮らすために「介護保険サービス」を上手に利用したいものです。
しかし介護保険サービスと言っても、人によって状況も状態も違いますので、具体的にどういった行動を起こし、どのようなサービスを選べばいいのかわからない、という方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、介護保険と配食サービスやその他のサービスを利用するための方法などについて紹介していきます。
目次
介護保健サービスの利用方法
介護保険サービスにはさまざまな種類がありますが、ひとりひとりの状態や環境に合ったサービスを選ぶことが重要です。
まずは相談することが大切です
私たちの暮らしの中で、家族に介護や支援が必要だなと感じたなら、自分だけ、家族だけで悩んだり考えたりするのではなく、次の2つの窓口へ相談してみましょう。
・地域包括支援センター
お住まいの地域ごとにあります。
要支援・要介護認定を受けていない方でも、高齢者の介護や支援についての相談を気軽にすることができます。
所在地や連絡先は、お住まいの自治体窓口に問い合わせましょう。各市区町村のホームページにも記載されていることがあります。
・一般介護予防事業
65歳以上の人で第1号被保険者の方であれば、原則としてどなたでも相談や予防活動に参加できます。
(地域によっては利用対象者や参加条件が決まっていますので、確認しておきましょう。)
自治体が配布する情報誌や役所の介護や福祉関係、または健康保険関係の窓口、地域包括支援センターなどで、利用できる内容を知ることができます。
このように介護や支援が必要になったときは各自治体に気軽に相談できる体制が整っています。
従来は、介護は家族の問題と捉えられがちでしたが、現在は、社会全体で高齢者を支援することを目的として、介護保険制度が整っています。
高齢者の介護や支援は長期的な視点を持つことも必要です。
早期の段階から介護の専門職に相談し、アドバイスをもらうことが安心して暮らしていける秘訣だと言えるでしょう。
申請しないとサービスは受けられません
介護保険サービスを利用するためには、介護保険認定を受けることが必要です。
(1)申請する
本人またはご家族からお住まいの自治体窓口へ「要支援・要介護認定」の申請を行いましょう。
申請には、以下のものが必要になります。
・要介護・要支援認定申請書(役所の窓口へ行くともらえます。)
・介護保険被保険者証(本人がお持ちです。)
・健康保険被保険者証(第2号の方の場合。)
・その他(地域によってはアンケートなどがあります。)
また、本人、代理の方の身元を確認するために「マイナンバー」が確認できる書類も必要になりますので用意しておきましょう。
(2)医師の意見書
そして、ここでもう一つ必要なことがあります。それは「主治医意見書」という、本人の体の状態を医師が診て結果を記した書類が必要になることです。
「かかりつけ医」がいる場合は、前もって「意見書」を書いてもらえるのか確認しておくと安心です。
「かかりつけ医」がいない、場合は、市区町村から紹介された医療機関を受診する必要があります。
(3)認定調査
申請からしばらくすると、調査員が本人の自宅などを訪問し、心身の状態を把握するために聞き取りを行います。
要介護度の判定が適切に行われるようにするため、本人が答える内容をしっかりと家族も聞いておき、必要に応じて補足説明をしましょう。
誰でも初めて会う人には警戒心を持ってしまうため、すぐに本音をさらけ出すことは難しいものです。
ご本人の心身の状態や日常の様子などを適切に調査員に伝えることが、適切な要介護度の判定につながります。
(4)コンピュータ判定(一次判定)
公平な判断をするため、訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、判定します。
(5)介護認定審査会(二次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づいて、医療や福祉などの専門家で構成される介護認定審査会によって、要介護度の判定が行われます。
認定結果で利用できるサービスが変わります
介護認定審査会の判定結果に基づいて市区町村が要介護認定を行い、原則として30日以内に申請者に認定結果が通知されます。
もし、通知された結果と本人の状態が一致していない場合は、申し立てをすることができます。その場合は自治体の窓口へ相談してください。
(1)要介護認定
要介護認定は、要支援1・2、要介護1~5の7段階に分かれています。どの要介護区分にも当てはまらない場合は「非該当」とされます。
「要支援」は基本的には自分だけで日常生活を送ることが可能で、部分的に支援が必要な状態です。
「要介護」は運動機能や思考力、理解力などの認知機能に低下が生じ、自分だけで日常生活を送ることが困難な状態です。
介護度が高くなるにつれて必要な介助の量が増加していると考えられます。要介護区分の目安は次の通りです。
・非該当:日常生活において支援が必要ない状態です。
調理や買い物、掃除の他、公共交通機関を利用しての外出や服薬管理など、複雑な思考や選択が問題なく行える状態です。
・要支援1:基本的な日常生活動作に大きな問題はありませんが、一部の動作に見守りや手助けが必要な状態です。
適切な介護予防サービスを利用することで、現状の維持や改善を図ることが重要です。
・要支援2:歩行や立ち上がりの動作が不安定であり、今後介護が必要となる可能性が高いと考えられる状態です。
日常的に介助が必要ではなくても、心身状態の悪化を防ぐために積極的な介護予防の取り組みが必要と考えられます。
・要介護1:歩行や立ち上がりの動作に一部介助が必要で、日常生活にも支援が必要な状態です。
ある程度の家事や食事や入浴、排せつなど、身の回りの基本的な日常生活は可能でも、複雑な動作が難しくなります。
認知機能に軽度の低下がみられるため、部分的に介助が必要です。
・要介護2:要介護1よりも日常生活の中で多くの支援が必要であり、認知機能の低下がみられる状態です。
見守りや介助の必要が増し、食事や入浴、排せつなどの動作にも介助が必要です。
・要介護3:日常生活動作(ADL)の全般に介助が必要であり、歩行や立ち上がりには杖や歩行器、車いすなどが必要となるケースも多くなります。
認知機能が低下し、日常生活の中でも常に見守りや介助が必要となるため、介護者への負担も増えていきます。
・要介護4:生活のあらゆる場面で介助が必要であり、思考力や理解力にも著しく低下が認められる状態です。
一部の動作や、一定の意思疎通は可能ですが、身体機能と認知機能の低下によって介護者の負担は大きくなります。
・要介護5:日常生活全般に介助が必要であり、意思の疎通も困難となることがあります。
1日の多くの時間を座った状態や寝た状態で過ごし、食事や排せつなどにも困難が生じる可能性があります。
(2)介護サービス計画書(ケアプラン)を作る
介護サービスを利用するときには、要介護認定を受けたご本人の心身の状態に合った介護サービスを検討する必要があります。
どのサービスをどのように利用するかを、ご本人やご家族の希望なども考慮しながら、ケアマネージャーがケアプランを作成します。
要支援1・2の場合は地域包括支援センターが介護予防サービス計画書を作成し、要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーへ依頼します。
(3)介護サービスを利用する
ケアプランに基づいたサービスを利用します。
要支援1・2と認定された方が利用できるサービスは「予防給付」、要介護1~5と認定された方が利用できるサービスは「介護給付」と呼ばれます。
介護サービスの内容は、いくつかの種類に分けることができ、必要に応じて、これらを組み合わせて利用することもできます。
・居宅介護支援:介護サービスを利用についての相談やケアプランの作成
・自宅で受けるサービス:訪問介護、訪問入浴、訪問介護など
・施設などに通うサービス:通所介護(デイサービス)、通所リハビリなど
・施設などに宿泊(または生活)をするサービス:期入所生活介護(ショートステイ)、老人ホーム入所など
・福祉用具にかかわるサービス:杖やシルバーカーなど福祉用具の貸与、販売など
(4)更新が必要
介護認定には有効期間があります。
有効期間が過ぎると介護サービスを利用することができなくなるため、有効期間が満了する前に更新認定の申請が必要です。
新規または変更の場合、有効期間は原則6か月ですが、介護認定を受けた方の状態に応じて、3~12か月の期間で設定することができます。
有効期間満了における更新申請は、原則として12か月で、介護認定を受けた方の状態に応じて3~24か月まで設定できます。
また有効期間の途中でも、介護認定を受けた方の心身の状態に大きく変化が生じたときには、要介護認定の変更(区分変更)を申請することができます。
サービス利用の目安
高齢者の心身の状態に応じたサービス利用の目安を見ていきます。
一般介護予防事業
65歳以上のすべての方を対象に、自治体や地域により要介護状態への進行予防を目的として介護予防サービスが提供されています。
一般予防事業には5種類あり、必要なものを組み合わせて実施します。
(1)介護予防把握事業
厚生労働省が作成したチェックリストなどから収集した情報を活用して、低栄養や引きこもりなどの現状を把握して、地域住民主体の介護予防活動へつなげます。
(2)介護予防普及啓発事業
パンフレットの配布や介護予防教室や講演会、相談会などを開催して、介護予防活動を普及・啓発します。
(3)地域介護予防活動支援事業
地域住民が主体で実施される運動や趣味の活動のうち、市区町村によって介護予防に値すると判断された活動は、活動の継続が支援されます。
(4)一般介護予防事業評価事業
「介護保険事業計画」に定める目標値の達成状況などを検証し、評価・改善をします。
(5)地域リハビリテーション活動支援事業
リハビリテーションの専門職などとのかかわりを促進し、地域の介護予防の取り組みを強化します。
費用は自治体によって異なり、教材費や材料費などの実費以外は原則として無料で参加できることが多いようですが、サービスの種類によっては1~3割の費用負担が必要なこともあります。
介護予防・生活支援事業
要支援1・2の方が対象です。運動機能や心身の状態の改善と悪化の予防を目的とした支援が行われます。
ケアプランの作成は無料ですが、その他のサービスは1~3割の自己負担があり、実際の支払金額は自治体によっても異なることがあります。
(1)ケアプランの作成
地域包括支援センターの職員などが介護予防ケアプランを作成します。
(2)訪問型サービス
ホームヘルパーなどが自宅を訪問して、家事などの生活支援を行います。
(3)通所型サービス
デイサービスなどの施設に通って、入浴や食事、機能訓練などの支援を受けることができます。
(4)その他のサービス
市区町村が独自に提供するサービスです。内容は市区町村ごとに異なることがあるので、担当窓口や地域包括支援センターなどに問い合わせましょう。
介護保険サービス
原則として要介護1~5の方が対象の介護保険適用のサービスです。
費用は介護保険料と国・自治体の財源によってまかなわれており、原則として1~3割の自己負担で利用できます。
具体的な自己負担額は、介護度などの条件によって異なります。
(1)居宅サービス
自宅に住んだまま受けられる介護サービスです。とても多くの種類がありますが、大きく「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」に分けられます。
・訪問サービス
自宅に訪問して、買い物や掃除、調理などの生活支援や、入浴、排せつなどの介護、医療的ケアが必要な方の看護、リハビリなどを行うサービスです。
・通所サービス
施設に通って日中を過ごし、食事、排せつ、入浴の他、健康管理やリハビリ、レクリエーションなどを行うサービスです。
・短期入所サービス
一定期間施設に宿泊して、食事、排せつ、入浴の他、健康管理やリハビリ、レクリエーションなどを行うサービスです。
(2)地域密着型サービス
住み慣れた自宅のある近隣の地域で生活が継続できるように、施設や事業所のある市区町村の要介護者(要支援者)に提供されるサービスです。
・訪問・通所型サービス
自宅で生活する方を対象にした地域密着型の訪問・通所型サービスです。
訪問あるいは施設に受け入れて、必要な生活支援や介護、医療的ケアなどを行うサービスです。
・認知症対応型サービス
認知症の方を対象に、生活支援や認知症ケアなどを行うサービスです。
・施設・特定施設型サービス
特別養護老人ホームや有料老人ホームに入居している方を対象に、必要な生活支援や食事、排せつ、入浴、医療的ケアやリハビリなどを提供するサービスです。
(3)施設サービス
主に「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」などに入所している方を対象に行うサービスです。
利用には上限があることも知っておこう
介護保険でサービスを利用する場合、要支援・要介護の区分によって、1ヶ月の支給限度額が設定されています。
この限度額を超えて介護サービスを利用された場合には、超えた分の費用は全額利用者負担になります。
支給限度額は介護度などの条件によって異なるため、具体的な金額についてはケアマネージャーなどに問い合わせましょう。
生活の中で利用できるサービス
ご自宅で暮らされる中で、車いすや歩行器など「福祉用具」や、暮らしやすくするためのリフォームを検討されることもあるでしょう。
自治体や要支援・要介護の区分によって利用できるもの、できないものがありますが、ケアマネージャーさんと相談しながら利用することで、安心して暮らせるように整っていきます。
福祉用具のレンタルや購入
代表的な用具としては、
・車いす
・歩行器
・杖
・特殊寝台
・床ずれ防止用具
・移動用リフト
他にもいろいろな福祉用具があります。
福祉用具の販売店やレンタル業者には福祉住環境コーディネーターの資格を持った職員がいることがあります。
またケアマネージャーの中でも福祉用具に詳しい人もいるので、相談してみましょう。
住宅改修の費用(リフォーム)
手すりの取り付けや床の段差解消は、ケガを防止するためにもやっておきたいところです。
こういった住宅改修の費用も上限がありますが、介護保険を利用して負担を軽減して安全な室内環境にすることができるでしょう。
ケアマネージャーさんへ相談し、介護での住宅改修が得意な工事業者さんを紹介してもらいましょう。
自治体への申請なども必要なので、経験を持った工事業者さんの方がスムーズで安心できます。
食事にかかわるサービス
食事は健康を維持するためだけではなく、大きな楽しみのひとつでもありますが、毎日3食の準備をすることは大きな負担にもなります。
・訪問介護の食事支援
訪問介護の生活援助として実施される場合は介護保険が適用されます。
訪問介護のスタッフ(ホームヘルパー)が食材の買い物や下ごしらえ、調理、後片付けなどを、高齢者ご本人と一緒に行い、ご本人やご家族ができないことを援助します。
料理の内容や味付け、栄養バランスなどにも配慮がされますが、あくまでも介護が必要なご本人の食事支援なので、同居しているご家族がいても、ご家族の分の食事などは含まれません。
日常生活の中で最低限必要であり、ご本人やご家族ができない部分を援助するというのが訪問介護の目的であり、具体的な援助内容はケアプランにも盛り込まれます。
・自治体による配食サービス費用の一部負担
民間の配食サービスの利用は介護保険の対象外なので、基本的には全額自己負担となりますが、要支援または要介護の認定を受けた方を対象に、自治体が配食サービスの費用を一部負担してくれることがあります。
「生活支援型配食サービス」や「高齢者配食サービス」などと呼ばれ、具体的な費用負担の割合や利用できる配食サービス業者、利用方法、利用条件などは自治体によって異なります。
配食サービスの利用を検討する場合には、市役所やケアマネージャーに問い合わせてみましょう。
配食サービスを選ぶポイント
配食サービスを利用するときには、ライフスタイルに合わせて、確認しておきたいポイントがいくつかあります。
・配達エリアと配達方法
配食サービスの業者が独自で配達する場合と、宅配業者が配達する場合があります。
配食サービス業者が直接配達する場合には配達エリアが決まっていることがあるため、お食事を届けてほしい場所が配達可能エリアかどうかを確認する必要があります。
また、お食事が冷凍で届く場合は、食事の時間にかかわらず受け取ることができますが、常温で届くお弁当の場合はすぐに食べることが前提のため、配達時間帯には在宅して受け取る必要があります。
・注文方法
注文方法は電話やインターネットなどがあります。
注文の単位も、1食ずつの注文や、1か月分、一定個数まとめて注文など、配食サービス業者によっても異なるので、食べる方の生活に合った注文方法ができるものを選びましょう。
また、急に必要になったときやキャンセルしたいときなど、何日前まで注文やキャンセルが可能なのかも確認しておくとよいでしょう。
・費用と支払方法
現在は配食サービス業者の数も多く、その価格もさまざまです。利用したい頻度と1食あたりの価格を併せて検討する必要があります。
支払いの方法も、配達時にその都度現金で支払う方法や1か月分を銀行振り込みやカードで支払う方法など、ほとんどの業者でいくつかの選択肢があります。
またお食事を食べるご本人に代わって、ご家族が支払うことも可能なので、詳細は配食サービスの業者に問い合わせてみましょう。
・おいしさ、調理が必要かどうか
やはり、おいしくなくては継続して食べることはできません。
配食サービス業者では、特別価格や無料の試食を用意していることがあるので、ぜひ利用して実際に食べてみましょう。
冷凍やレトルトで届く場合には、温めるなどの簡単な調理が必要となるため、安全に無理なく調理できるかどうかの確認も必要です。
またお弁当が冷凍か常温かにかかわらず、主食の付かないおかずのみ提供の場合もあります。
主食を自分で用意することで費用が軽減できることや量の調整が容易なことがメリットです。ただし、主食を別に用意する必要があります。
・食事の内容、食事形態
慢性疾患をお持ちの方は、栄養面に配慮が必要な場合もあります。
管理栄養士によって、エネルギーや塩分、たんぱく質などの栄養素が調整されたお食事を提供している配食サービス業者もあるので、確認してみましょう。
また、摂食嚥下機能の状態に合わせて食事形態を調整した、介護食の提供が可能な配食サービス業者もあります。
知っておくと便利!高齢者の福祉サービス
地域によっては独自の福祉サービスが提供されていることもあります。
自治体によってサービスの内容や費用、サービスを受けるための条件などが異なるため、市区町村の担当窓口やケアマネージャーに問い合わせてみましょう。
・軽度生活支援ヘルパー派遣事業
買い物や掃除、洗濯などを有料で援助してもらえます。
・ふとん水洗い乾燥サービス事業
快適な睡眠のために、寝具を清潔に保つことは大切です。
高齢になると、ふとんを干すことも大変な家事のひとつとなるため、効果的なサービスのひとつといえます。
・緊急通報システム
緊急通報装置を設置することで、体調の急変や災害時などの緊急事態に、民間の受信センターに通報できます。
・おむつの支給
大人用紙おむつやリハビリパンツ、パット類を配達してもらえます。また、おむつ代に補助が受けられることがあります。
・外出支援
運転免許を返納し、最寄りの駅やバス停まで歩くことが困難な高齢者などを対象に、タクシーの利用券やバスの乗車料金の助成が受けられることがあります。
介護保険サービスのまとめ
介護認定を受けるには申請が必要です。認定結果によって利用できるサービスが決まり、その他の条件によって自己負担額も変わります。
また、最後に紹介しました生活の中で利用できるサービス。こういったサービスの利用が可能なら検討してもらいたいと思います。
特に配食サービスは、
・安否確認
・会話による刺激
・人が訪ねてくる楽しみ
など、「食事が届く」ということ以外にもいくつかのメリットが期待できます。
生活に支援が必要な方それぞれに合った介護サービスを受けて、高齢になっても安心して暮らせる環境を作りましょう。
 まごころ弁当
まごころ弁当 配食のふれ愛
配食のふれ愛 宅食ライフ
宅食ライフ すくすく弁当
すくすく弁当 まごころケア食
まごころケア食 ライフミール
ライフミール わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん 運営会社
運営会社 こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ