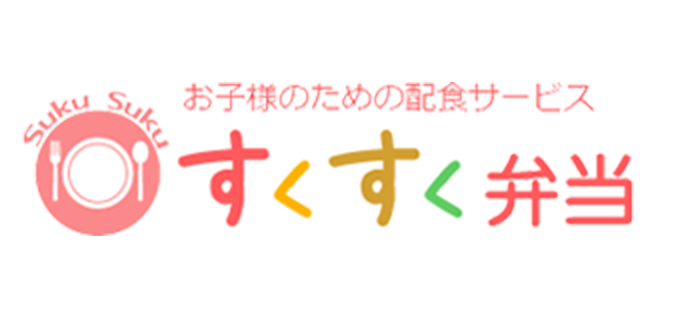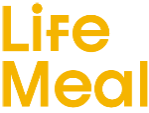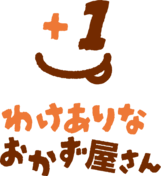こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!

和食は健康的な食事として世界的にも注目されています。2013年には、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されました。私たちが日々何気なく食べている「和食」の良さとは何か、改めて考えてみましょう。
目次
和食とはどんな料理?
和食とは特定の料理を指すものではなく、「日本人の伝統的な食文化」とされています。
精進料理や懐石料理など、形式を重んじ日本の風土や社会で発達してきた料理の他に、年中行事に合わせて伝統的に食されてきた食べ物や家庭食も含む、日本の食文化全体をあらわす言葉といえます。
和食の歴史と発達
和食の大きな特徴のひとつである米食の文化は、縄文時代に始まり、弥生時代にかけて日本中に広がりました。
その後奈良時代には、遣唐使によって中国から食材や調理方法が持ち込まれるようになりましたが、それらを食べることができたのは権力者たちの特権であり、中国由来の食文化は、遣唐使の廃止とともに廃れていきました。
日本独自の食文化が発達していくのは平安時代の中期以降のようです。
平安時代には食材の種類も限られており、調理方法も煮る・焼く・蒸す程度しかできませんでした。
調味料の種類も少なく、「だし」をとるという技法もなかったため、非常にシンプルな料理であったと考えられています。
鎌倉時代になって、再び中国から禅宗とともに「精進料理」が伝わりました。
大豆を使った料理や小麦粉で作られた麺類などが伝わり、調理方法や調理技術も格段に進歩しました。この頃から、炊いた米を主食とした和食の形が整い始めたようです。
室町時代には本膳料理、戦国時代には懐石料理といった、食材や調理方法、盛り付け、提供方法など、作法や決まりごとのある料理の形式が確立していきました。
本膳料理は武家がお客をもてなすための料理で、儀式としての要素が非常に強い料理様式です。
酒を中心とした「献部」と食事を主とする「膳部」から成り、献部は特に儀礼的要素が強く、三々九度は現在にも残っている形式のひとつです。
饗応の規模によって異なりますが、食事の合間には能が演じられるなどの催しもあり、全体が終了するまで夜を徹することもあったといわれています。
懐石料理は茶道の中から発達してきた料理であり、本膳料理のような堅苦しい作法には縛られず、千利休が大切にした「一期一会」の精神が生かされ、旬のものを積極的に取り入れるのが特徴といえます。
江戸時代の元禄期頃(1688~1704年)になると、それまで1日2食が普通だったのが、1日3食の食習慣が定着しました。
その理由はいくつか考えられますが、1657年の明暦の大火の復興にあたった肉体労働者が1日3食摂っていたことや、流通の発達によって外食産業が盛んになっていたこと、菜種油による照明が一般に利用されるようになり、夜の活動時間が長くなったことなど、さまざまな要因によって現在と同じような食習慣になっていったと考えられています。
柔軟性のある和食文化
日本の伝統的な食文化である和食は、その時代や環境に適応しながら変化し、発展してきました。
和食の代名詞ともいえる「寿司」や「天ぷら」も、実はそのルーツは海外にあるといわれます。
寿司は、稲作の伝来とともに大陸から伝わった「なれずし」が始まりとされていますし、天ぷらも17世紀に西洋から伝わった「フリッター」をアレンジしたものです。
和食は時代や環境、嗜好の変化や技術の発展などに応じて柔軟に変化・進化を続ける、生きた文化といえます。
和食の料理は今後もさらに工夫されたり、新しいものが取り入れられたりして変化していくかもしれません。
和食文化を継承していく上で大切なのは、一定の変化は柔軟に受け入れながらも和食文化の歴史を知り、つながれてきた日本人の基本的な精神を守っていくことです。
和食の日
一般社団法人和食文化国民会議が制定した「和食の日」があります。
和食の日は、「いい(11)に(2)ほんしょ(4)く」という語呂合わせから、11月24日となりました。
実りの季節、和食に特有の食材が豊かに収穫されるこの時季に、日本の食文化を見直して和食文化の保護・継承について考えることを目的として制定されました。
和食の特徴について
米食から生まれた感謝と祈り
原始の時代、もともとは自生していた米を採って食料としていましたが、今から約3千年前に朝鮮半島を経由して中国から稲作が伝わりました。
稲作によってその土地に定住するようになった日本人は農具や農法を発達させ、社会を形成していきました。
米は食料としてだけではなく、現在の税金のように国の財源として使われるようになり、経済の基礎にもなっていきます。
また日本人は1年に1回実りをもたらす米に神秘的な力を感じ、稲作や米を守る神を祀り、感謝をささげる農耕儀礼として、祭りやさまざまな行事が生まれていきます。
米食の文化は、米の持つ生命力にあやかり、収穫に感謝し健康に過ごせることを祈る文化であるといえます。
一汁三菜(いちじゅうさんさい)
もともとは本膳料理の献立のひとつで、ごはんと汁物、漬物に加えて、主菜・副菜・副々菜とおかずを3品揃えるという献立形式を指す言葉です。
懐石料理や会席料理でも基本は同様ですが、おかずの皿数や料理の調理方法、提供順などは、それぞれ異なる形式があります。
主食となるごはんは米と水だけで調理されるため、どんなおかずとも相性がよく、食べ飽きることがありません。
米の主な栄養素は炭水化物ですが、たんぱく質やビタミンB6、B1、マグネシウムや鉄などのミネラル、食物繊維も含みます。
しかしたんぱく質やビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素は、精米の際に取り除かれる糠層に多く含まれているため、栄養価では玄米の方が優れているといえます。
現在のように精米技術が進化する前は、精米後の白米にも糠や胚芽の残存が多く、自然と多くの栄養成分が摂れていたと考えられます。
ごはんを中心として、精米時に出る「糠」を活用した野菜の糠漬けや、大豆から作ったみそを使ったみそ汁、その他におかずを3品用意すれば、自然と栄養のバランスが整った食事となります。
だしの利用
和食の味付けの基本となるのは、かつお節や昆布などからとった「だし」です。
だしを使うことで油脂を使わなくてもおいしく調味できるので、エネルギー(カロリー)を抑えることができます。
昆布だしが使われ始めたのは室町時代の初期と考えられており、それより100年ほど後になってから、かつお節を使っただしが使われるようになったようです。
その後、江戸時代には昆布とかつお節の合わせだしが使われるようになり、現在に近いだしの取り方が行われていたと考えられます。
・かつお節
かつお節は、ゆでたかつおの身を燻してから乾燥させた保存食品です。
製造工程の違いで、カビ付けをして熟成したものには枯節(かれぶし)や本枯節(ほんかれぶし)、カビ付けをしないものを荒節(あらぶし)と呼びます。
かつお節のうま味成分はイノシン酸です。
・煮干し
煮干しは小魚を煮て干したものです。一般的にはイワシの煮干しを指しますが、地域によってはアジやサバも利用されています。
もともとは江戸時代に米作の肥料として生産された干鰯(ほしか)をだしに利用したと考えられています。
干鰯は大型のイワシが利用されていましたが、大量に獲れる小型のイワシはイリコとしてかつお節の代用として一般に普及していきました。
煮干しのうま味成分はイノシン酸です。
・昆布
昆布の歴史は古く、はっきりとした記録が残っていません。
北海道から北陸地方は昆布の陸揚げ地であることから昆布だしの文化が発達しており、比較的かつお節の需要が低い地域です。昆布のうま味成分はグルタミン酸です。
・干ししいたけ
干ししいたけには肉厚な冬菇(どんこ)や、かさの開いた香信(こうしん)などがあります。冷水で時間をかけ、ゆっくり戻す方が、うま味の強いだしがとれます。
干ししいたけのうま味成分はグアニル酸です。
・焼きあご
トビウオを焼いてから乾燥させたもので、特有の風味があります。焼きあごのうま味成分はイノシン酸です。
地域ごとの特徴
日本は南北に長い島国であることから、地理的にも気候的にも環境の異なる地域が、それぞれ独自の食習慣を育んできました。
同じ食材であっても、雪深い東北の地域と温暖な九州の地域では、保存方法や調理方法などが異なることがよくあります。
例えばお正月に食べる「お餅」も「東の角餅、西の丸餅」といわれ、お餅の形から異なります。
さらにお雑煮となると、日本各地でお餅の形はもちろん、味付けも、一緒に入れる食材もまさに千差万別といえます。
お雑煮はその土地の気候・環境、習慣、信仰など、さまざまな要因によって形成されており、まさに歴史と文化を反映しているといっても大げさではないのです。
食欲を増す盛り付け
見た目のおいしさを考えることも、和食の特徴のひとつです。できあがった料理と一緒に、彩や季節感も器に盛り込んでいきます。
伝統的な和食や懐石料理など、形式の整った料理のの盛り付けには一定の決まりもありますが、日常的に食べる和食では、いくつかのコツを覚えるだけで美しく盛り付けることができます。
・3を意識する
ひとつのお皿に数種類のお料理や食材を盛り付けるときは、構図を三角形にとり、3種類を盛り付けます。盛り付けは平面ではなく立体を意識して、山高に盛り付けるようにしましょう。
・青(緑)、黄、赤、白、黒(しょうおうしゃくびゃくこく)
料理の5色ともいわれます。1皿の中や1人分のお膳の中に、これらの色をバランスよく配置することで、盛り付けが華やかになります。
・量は控えめに
盛り付けは「余白3割」といいます。料理ののっていない、皿の余白を3割以上残しておくようにします。
大皿にある程度の量を入れる場合でも、山高に盛り付けて大皿や深鉢の内側が見えるようにしましょう。
汁物も同様に、お椀の7分目くらいによそう方が美しく、食べやすいものです。
年中行事
日本には、1年の間に実にたくさんの年中行事があります。年中行事とは、もともとは宮中で行われる行事や祭事のことをいいましたが、徐々に一般にも広がりました。
年中行事の日は「ハレの日」とも呼ばれ、「神様に感謝し、ごちそうをささげる日」でもありました。
普段の食事にはないごちそうを並べてお供えし、それをいただくことで家内安全、無病息災、五穀豊穣などを祈ります。
年中行事にはそれぞれに行事食があり、その食材や料理には意味があります。
<年中行事と食べ物>
| 日にち | 行事名 | 食べ物 | 意味合い |
| 1月1~3日 | お正月 | おせち料理
| 年の初めを祝う料理です。黒豆や数の子、昆布巻き、伊達巻、田作りなど、それぞれに長寿や子宝、五穀豊穣などの意味があり、願いが込められています。 |
| お雑煮 | 旧年の収穫や無事に感謝し、新年の豊作や家内安全を祈ります。 | ||
| 1月7日 | 七草 | 七草粥 | 青菜の不足しがちな冬の栄養補給と、新年の無病息災を願います。 |
| 1月11日 | 鏡開き | おしるこ | 年神様が宿っていた鏡もちを食べることでその力を授かり、新年の無病息災を祈ります。 |
| 2月3日 | 節分 | 恵方巻 | 巻き寿司を切らずに食べるのは「縁を切らない」という意味があります。その年の恵方を向いて無言で1本を食べきり、1年の幸運を祈ります。 |
| イワシ | イワシは臭うので、鬼が寄ってこないという魔除けの意味があります。 | ||
| 3月3日 | ひな祭り (桃の節句) | 蛤 | 二枚貝は対になっている貝同士でないとぴったり合わないことから、貞操の象徴と仲の良い夫婦をあらわすといわれます。 |
| ひしもち | 上からピンク・白・緑の色が重ねられています。桃の花が咲く木の下に溶け残った雪と、雪の下に生える新緑をあらわしています。 | ||
| ひなあられ | ひな人形に春の景色を見せてあげるという風習から、ひなあられを持って出かけたといわれています。 | ||
| 3月17~23日 | 春の彼岸 | ぼた餅 | あずきの色には災いが身に降りかからないようにするおまじないの効果があるといわれます。春の彼岸には牡丹の花に見立ててぼた餅と呼びます。 |
| 5月5日 | 子供の日 (端午の節句) | 柏餅 | 柏の葉は新芽が出ないと古い葉が落ちないことから、家系が絶えないようにという願いが込められています。 |
| 7月7日 | 七夕 | そうめん | 後醍醐天皇の時代、宮中の七夕行事ではそうめんの原型である「索餅(さくべい)」を供えて霊鬼神の祟りを沈めたことから始まっています。 |
| 7月21日 | 土用の丑 | うなぎ | 土用の丑は季節の変わり目にあたるため、栄養豊富なウナギを食べて体調を整えようという考えがありました。 |
| 9月9日 | 重陽の節句 | 菊酒 | 延命、不良長寿の薬草として中国から伝わった菊を酒に浮かべ、縁起酒として供されます。 |
| 9月19~25日 | 秋の彼岸 | おはぎ | 意味は春の彼岸と同様ですが、秋は萩の花に見立てておはぎと呼びます。 |
| 10月1日 | 十五夜 | 月見団子 | 満月に見立てた丸い団子を月に向かって供えることで、その年の収穫を祝います。 |
| 11月15日 | 七五三 | 千歳あめ | 千歳は千年をあらわし、子どもの健やかな成長と長寿を祈って、子どもの喜ぶあめを長い棒状にしたといわれます。 |
| 12月21日 | 冬至 | かぼちゃ | 新鮮な野菜がなくなる時期にも、保存のきくかぼちゃは貴重な栄養源であったことから、この時期に栄養豊富なかぼちゃを食べることが習わしとなりました。 |
| 12月31日 | 大晦日 | 年越しそば | そばは切れやすいことから、今年の不運は切り捨てて新しい年を迎え、そばのように細く長く過ごせることを願って食べます。 |
※表は2020年(令和2年)の日にちです。年や地域によって、日にちが変わる行事もあります。
表では一般的な年中行事をあげましたが、同じ行事であっても地域によって食べるものやその意味合いが異なる場合もあります。
生まれ育った土地の年中行事や、そのときに食べるものについて知り、次の世代に伝えていくことも大切です。
和食がユネスコ無形文化遺産に登録
2013年12月4日、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
「和食」という料理としてというよりも、「自然を尊重する日本人の精神を体現した食に関する社会的習慣」という意味合いで位置づけられています。
農林水産省のウェブサイトです。和食を含め、世界のユネスコ無形文化遺産登録された食文化について紹介されています。ご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1402/spe1_01.html
登録理由1:新鮮で多様な食材とその持ち味の尊重
日本の国土は南北に長いため、その地域ごとに海や山、里など表情豊かな自然を見ることができます。
それぞれの土地に根差した四季折々の多様な食材を用いて、素材の味わいを生かした調理方法や調理道具が発達してきました。
登録理由2:栄養バランスに優れた健康的な食生活
一汁三菜を基本とした日本の食事スタイルは、理想的な栄養バランスを作ることができるといわれています。
主食となる米を中心として、だしの「うま味」をうまく使い、動物性油脂の少ない食生活を実現でき、日本人の長寿や肥満防止に役立っていると考えられます。
【配食のふれ愛】では、栄養バランスの良いメニューをご提供しています。ただいま無料試食キャンペーン中です。ぜひ利用ください。
https://www.h-fureai.com/trial/
登録理由3:自然の美しさや季節の移ろいを表現した盛り付け
食事で自然の美しさや四季の移ろいを表現することは、和食の大きな特徴のひとつといえます。
季節の花や葉を盛り付けに使ったり、季節ごとに器や調度品を変えるなどして、季節感を楽しみます。
登録理由4:正月行事などの年中行事との関り
日本の食文化は、年中行事と密接にかかわりながら育まれてきました。
自然の恵みを分け合い、食の時間を共に過ごすことは、家族や地域などの人と人との絆を深めます。
初節句や七五三から重陽の節句まで、人生の節目の儀礼においても、和食は密接なかかわりを持っています。
和食と食育について
ユネスコ無形文化遺産に登録されたことや、健康志向によって世界的には和食が注目を浴びている一方で、国内では和食への関心が薄れていたり、家庭で和食が食される機会が減少しているといわれます。
子どものころから和食に触れ、和食の理解を深めることは、食育の目的のひとつです。
食育とは
食育は、偏った栄養摂取や朝食の欠食、孤食などが要因となっておこる食生活の乱れや、肥満、痩身など、子どもたちの健康を取り巻く問題を解決するために重要な役割を果たすと考えられ、2005年(平成17年)に食育基本法、翌年に食育推進基本計画が制定されました。
成長期の子どもに食育を実践することで、子どもが生涯健康に生きていくための基礎を作り、適切な食習慣を子どものころに身につけることが目的です。
具体的には次のような項目が挙げられます。
・食べ物を大事にする感謝の心
・好き嫌いしないで栄養バランスよく食べること
・食事のマナーなどの社会性
・食事の重要性や心身の健康
・安全や品質など食品を選択する能力
・地域の産物や歴史など食文化の理解
特に最後の項目では、和食についての理解が必要といえます。
子どもに伝えたい和食とは
・食事の挨拶
日本には、食事の前後に「いただきます」「ごちそうさま」という挨拶があります。
どちらも食材そのものや、その食事ができるまでにかかわった人たちへの感謝の気持ちを表す言葉ですが、英語では直訳できる単語はありません。
信仰する宗教によっては食事の前にお祈りを捧げますが、「いただきます」「ごちそうさま」には、そのお祈りと通じる意味があるともいえます。
・多彩な食材と季節感
日本には海や山など、その土地ならではの自然で育った食文化があります。さらに四季ごとに旬の食材を利用して季節感を楽しみます。
自分が生まれ育った地域に特有の食文化や郷土料理、季節ごとに食べる食材や料理など、子どものころから生活の中で繰り返し身につけた食習慣は、大人になっても覚えているものです。
・行事食の伝承
和食には季節ごとの年中行事や、人生の節目に行われる行事のときに食べる行事食があります。
お正月に食べるおせち料理や、大みそかに食べる年越しそばなどは、地域ごとに特徴がありますし、お食い初めや七五三、還暦などの行事には家族の幸せや健康を願う意味が込められています。
・多彩な調理方法とうま味の活用
和食では、同じ食材でも違う調理方法で作る料理が多くあります。それはおいしさにつながることはもちろんですが、食材を無駄にしないために考えられた方法でもあります。
また、和食の最大の特徴ともいえるのが「うま味」であり、うま味を利用することで油脂の使用が控えられます。
Let‘s和ごはんプロジェクト
和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて5周年を迎えた2018年に始まった、官民協働のプロジェクトで、味覚が形成される子どものうちから、身近で手軽に健康的な「和ごはん」を食べる機会を増やすことで、和食文化の保護や継承につなげるのが目的です。
11月を「和ごはん月間」として、プロジェクトメンバーの企業や団体がイベントや企画を行っています。プロジェクトメンバーの活動内容は、
1.内食分野において、従来と比較して簡単に和ごはんが調理できる商品の開発、当該商品販売促進、簡単に作れる和ごはんのレシピの開発・発言を行うなど子どもたちや子育て世代に対して身近で手軽に和ごはんを食べる機会を増やしてもらうための活動。
2.中食分野において、和ごはん商品を拡充・展開するなど、子どもたちや子育て世代に対して身近で手軽に和ごはんを食べる機会を増やしてもらうための活動。
3.外食分野において子ども向け和ごはんメニュー、年中行事や人生の節目を祝う和ごはんを提供するなど、子どもたちや子育て世代に対して身近で手軽に和ごはんを食べる機会を増やしてもらうための活動。
4.その他、子どもたちや子育て世代に対して身近で手軽に和ごはんを食べる機会を増やしてもらうための活動。
和食に関するまとめ
近年、海外では日本食ブームが高まっており、「スシ(寿司)」「ショウユ(しょう油)」「テンプラ(天ぷら)」など、和食をあらわす言葉のいくつかは、そのまま海外でも通用するようになっています。
しかし一方で、日本国内ではお正月のおせち料理など、伝統的な食習慣が薄れつつあるという現状があります。
和食は世界に誇れる食文化です。和食の良さを再確認し、日々の生活の中で次世代へと伝えていきましょう。
【配食のふれ愛】では、栄養バランスの良いメニューをご提供しています。ただいま無料試食キャンペーン中です。ぜひ利用ください。
 まごころ弁当
まごころ弁当  配食のふれ愛
配食のふれ愛  宅食ライフ
宅食ライフ  すくすく弁当
すくすく弁当  まごころケア食
まごころケア食  ライフミール
ライフミール  わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん  運営会社
運営会社  こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ