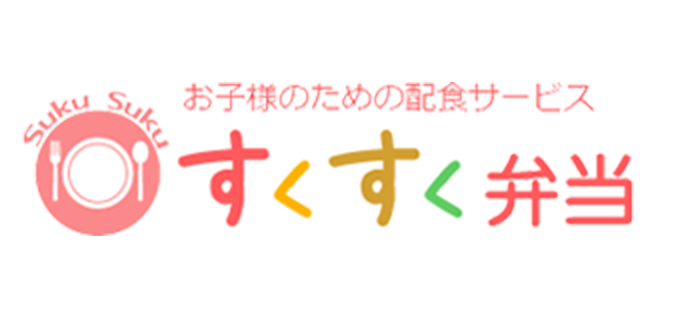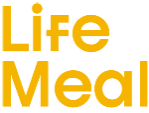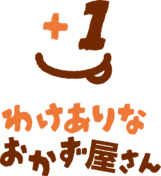こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!
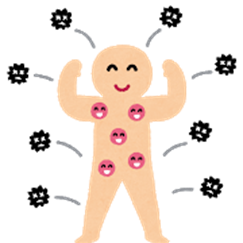
「免疫」や「免疫力」という言葉は一般的によく聞かれますが、人の体の中でどのような働きをしているのでしょうか?さまざまな病気から体を守る、免疫の仕組みについてまとめます。
免疫とはどんな働き?
免疫とは、その漢字が表すように「疫(病気)を免れる」ことです。免疫の機能があることによって同じ病原体による病気に再びかからなかったり、かかっても軽く済みます。また、免疫の仕組みによって引きおこされる疾患もあります。
免疫とは
免疫は自分の体内に入ってきた自分以外のもの(非自己)を排除する仕組みです。体内に入ってきた細菌やウイルスを自分ではない異物と判断して攻撃して排除したり、自分自身の細胞が間違って変化した「勝手に増える狂った細胞」であるがん細胞も、免疫が攻撃します。免疫自身には、体内に入ってきた異物が自分にとって有害か無害かを判断する能力はありません。例えば臓器移植の際に、親子や兄弟などの近い家族から臓器提供を受けたとしても、免疫は移植された臓器を自分ではない異物として攻撃し、拒絶反応がおこります。その拒絶反応を抑えるためには、一時的に免疫の働きを抑制する処置が必要となります。
また、栄養を摂取するために体内にとり込んだ(食べた)食べ物は、本来は無視してもいい異物であるにもかかわらず、免疫が攻撃してしまうことで症状がおこるのが食物アレルギーです。免疫の仕組みは人の体を異物から守るために必要ですが、免疫の仕組みに間違いがおこると、治りにくい疾患になることもあります。
免疫とワクチン
一度かかった病気に対して、同じ病原体が再び体内に侵入したときに攻撃する仕組みができますが、この仕組みは免疫によるものです。免疫は、一度体内に入ってきた病原体を記憶して、次に体内に入ってきたいときには迷わず攻撃します。この仕組みは後天的に備わる免疫の機能で、「獲得免疫」といいます。そしてこの仕組みを利用して病気を予防するのがワクチンです。ワクチンには主に3種類あります。
・生ワクチン:病原体は生きているが、ウイルスや細菌が持っている病原性を弱めたものです。生ワクチンを予防接種すると、その病気にかかったのとほぼ同等の免疫力がつきます。病原性を弱くしたウイルスや細菌が体の中で徐々に増えるので、自然にかかったときと同じような症状が出ることがあります。
・不活化ワクチン:病原性を無くした細菌やウイルスの一部を使います。生ワクチンに比べて免疫力がつきにくいので、複数回の摂取が必要です。
・トキソイド:細菌が産生する毒素(トキシン)を取り出し、免疫を作る力は残して毒素を無くしたものです。
【ワクチンの種類】
| 製造方法 | 特徴 | |
| 生 ワ ク チ ン | 病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて、病原性を無くしたものを原料として作られています。病原体は弱いけど生きている状態です。 | 毒性を弱めたウイルスや細菌が、体内で増殖して免疫を高めていくので、接種の回数は少なくて済みます。十分に免疫ができるまでは約1か月かかります。 |
| 不 活 化 ワ ク チ ン | 病原体となるウイルスや細菌の感染する能力を失わせた(不活化した)ものを原材料として作られます。 | 自然感染や生ワクチンに比べて生み出される免疫力が弱いため、1回の摂取では十分ではなく、何回かの追加接種が必要となります。摂取回数はワクチンによって異なります。 |
| ト キ ソ イ ド | 病原体となる細菌が作る毒素だけを取り出して、毒性を無くして作られます。 | 不活化ワクチンと同じように、複数回接種して免疫をつけます。 |
https://www.nibiohn.go.jp/CVAR/vaccine.html
ワクチン・アジュバント研究センター(CVAR)のウェブサイトです。ワクチンについて詳しく説明されていますので、ご参照ください。
免疫の種類について
免疫には生まれながらに持っている自然免疫と、後天的に備わっていく獲得免疫があります。
自然免疫
自然免疫は生まれながらに持っている免疫で、免疫の前衛部隊といえます。体内に入ってきた異物をみつけると、まず自然免疫が向かっていきます。自然免疫を担当しているのがマクロファージやNK細胞で、初めて出会った抗原(免疫反応を引きおこす原因となる物質)に素早く反応します。自然免疫には、異物の種類を識別する能力(特異性)はないといわれていましたが、自然免疫にも細菌やウイルス、がん細胞に対する受容体が発現することがわかっていて、自然免疫にも弱い特異性があり、侵入した異物を大まかに認識していることが明らかとなっています。
また自然免疫を担う細胞は、一つの細胞に複数の異物に対する受容体が発現し、一つの細胞が複数の異物に対して反応できることも特徴です。自然免疫は不安定で、いろいろな刺激によって反応性が変化します。例えば、衛生環境の整っていない外国の地域に行く際にワクチン接種を求められるのは、過酷な環境下で自然免疫が低下し、初期の防御機能が破綻したとしても、ワクチンによって得た獲得免疫によって感染症を防ぐのが目的です。
獲得免疫
「同じ病原体による病気に再びかからない」のは、獲得免疫の仕組みによる効果といえます。獲得免疫は初めて体内に入ってきた抗原を記憶し、二度目に同じ異物が体内に侵入してきたときには厳密に見分けて素早く確実に反応します。この仕組みを利用して特定の感染症を予防するのがワクチンです。獲得免疫を担うのはT細胞やB細胞で、抗原のわずかな違いまで見分けるため、一つの細胞は一つのの抗原にしか反応できません。
インフルエンザワクチンを毎年接種するのは、流行するインフルエンザウイルスが変異するためです。獲得免疫の厳密な抗原認識をつかさどっているのが、T細胞の表面に発現するT細胞レセプターや、B細胞が産生する抗体のB細胞レセプターです。一つのT細胞やB細胞には一種類のT細胞レセプターや抗体(B細胞レセプター)しか発現できないため、一つの細胞は一つのの抗原にしか反応できません。しかしこの仕組みによって、獲得免疫全体としては非常に多くの抗原に反応することが可能となります。獲得免疫は生命を維持するにあたり、極めて異常な状態以外ではその活性は維持されるため、安定した反応が期待できます。
【自然免疫と獲得免疫の比較】
| 担当する細胞 | 特徴 | |
| 自 然 免 疫 | マクロファージ | 細菌などの貪食。 |
| NK細胞 | がん細胞やウイルス感染細胞の傷害。 | |
| 樹状細胞 | 抗原提示により、自然免疫と獲得免疫の橋渡しをする。 | |
| 獲 得 免 疫 | T細胞
CD8T細胞 → CD4T細胞 → | 胸腺で分化し、CD8T細胞とCD4T細胞で機能が異なる。 |
| がん細胞やウイルス感染細胞の傷害。 | ||
| 他の免疫担当細胞を助ける。 | ||
| B細胞 | 抗体の産生 |
自然免疫と獲得免疫の連携
体内に自分ではない異物が侵入すると始めに自然免疫が素早く反応し、弱い敵に対しては自然免疫の力で排除することができます。この自然免疫の働きは24時間常に行われていると考えられ、そのために健康な状態が維持されているといえます。しかし、時折侵入してくる強い敵や多数の敵に対しては、自然免疫だけでは戦えないことがあります。その場合には、樹状細胞と呼ばれるマクロファージ系の細胞が伝令役となり、獲得免疫に敵の情報を伝えに行きます。この樹状細胞による抗原提示によってT細胞(主にヘルパーT細胞)やB細胞が活性化し、異物を排除します。
一度働いた獲得免疫(T細胞とB細胞)の一部は休眠状態となり、次に同じ異物が侵入したときには樹状細胞の伝令を待たずに、急激に強く反応します。強い獲得免疫は通常は休んでいて、時折侵入してくる特定の強い敵を排除するときにだけ働いているといえます。
獲得免疫の異常
前述のように、獲得免疫は自然免疫と比較して格段に強い機能を持っていて、この強力な作用によって病原体が体外に排除されています。しかし一方では、獲得免疫の異常な活性化が疾患の原因となることがあります。
T細胞は分化の過程で、自己の正常な細胞を攻撃しないように制御されていますが、何らかの要因でこの制御が外れたときに、間違って自己の正常な細胞を攻撃してしまうことでおこる疾患が自己免疫疾患です。
リウマチはその代表で、獲得免疫が関節の正常な細胞を攻撃することで発症します。また、非自己ではあっても無視してよいものに対して獲得免疫が過剰に反応することでおきるのがアレルギーです。
「免疫力を上げる」とはどういうことか
よく、「免疫力を上げる」「免疫力が高い」などという言い方が聞かれますが、一般的にはどのようなことを意味しているのでしょうか。獲得免疫は、一度かかったりワクチンを接種することで特定の異物に対して戦う力を備えることですから、乳幼児が数種類のワクチンを接種するのは、特定の疾患に対して免疫力を上げるためと考えることもできます。
自然免疫は、体内に侵入してくる敵と常に戦っていますが、生活環境や睡眠、食事、運動、ストレス、飲酒や喫煙など、さまざまな条件によって変化しやすく不安定で、体調がその人の現状の自然免疫の働きを反映しているともいえます。つまり、風邪をひいたり体調不良を感じずに生活できているときは自然免疫の力が適切に機能していて、体調が悪くなったときには自然免疫の力が弱まっていたのであろうと考えることができます。
日常生活の中で一般的に言われる「免疫力を上げる」「免疫力が高い」ということは、生活の中で自然免疫の働きを強化して、自然免疫によって病気にかかりにくかったり、かかってもすぐに治る状態を意味していると考えることができます。
自然免疫『NK細胞』
NK細胞は、常に体を守るために働いている自然免疫に属しています。本名はナチュラルキラー(Natural Killer)細胞、生まれながらの殺し屋といえます。
NK細胞の働き
名前が表すように、初めてであったウイルス感染細胞やがん細胞を傷害・殺傷します。また、他の免疫担当細胞を活性化する物質である、サイトカインを産生する働きも持っています。近年はNK細胞の仲間ともいえるいろいろな機能を持った自然免疫系の細胞が発見されており、自然免疫系がより複雑なものであることがわかってきています。NK細胞にもある程度の記憶力があり、一度感染したウイルスに対して、二度目以降の感染には素早く、強く反応できることがわかっています。
NK活性とは
NK活性とは、NK細胞が出会った標的となる細胞(非自己である敵)を、4時間で傷害(殺傷)できる能力のことで、自然免疫の力の評価の指標とされます。一般的にはNK活性40%前後が健常な人の平均値といわれています。NK活性40%とは、例えば体内で発生したがん細胞を4時間で40%を殺傷し、次の4時間でまた残ったがん細胞の40%、次の4時間でまた残ったがんの40%…と攻撃していくと、24時間で約97%のがん細胞を殺傷できることになり、がんを発症しないためには十分な能力ということができます。
NK細胞の効果
先天的にNK細胞を欠損している、またはNK活性が無いという疾患があります。その場合、出生直後からウイルス感染を繰り返し、幼少期のうちにウイルス感染症で命を落としてしまうケースが多くあります。他にもNK活性が低下している人の場合では、ウイルス感染を頻発したり、症状が回復しにくい、重篤な状態に陥るといったことがおこります。
さらに疫学的な研究では、NK活性が低い人はNK活性が平均的な人や平均よりも高い人と比較すると、がんの発生率が高いこともわかっています。これらのことから、NK細胞はウイルス感染の初期防御や発がんを監視する機能、がんの転移抑制にも重要な役割を担っていると考えられています。
NK細胞はどうやって敵を見分けるか
NK細胞には多くの受容体が発現し、受容体から受け取る刺激のバランスで、自己の細胞を攻撃しないように制御されています。正常な細胞は、「MHC Class Ⅰ」という自己であるという印を発現することで、NK細胞は正常な自己であると認識できます。がん細胞では、このMHC Class Ⅰという自己の印を失っているため、NK細胞は敵とみなして攻撃します。
免疫に関するまとめ
自助努力で高められる免疫はNK細胞を含む自然免疫です。獲得免疫のように特定の疾患に対して強力な効果はありませんが、幅広くさまざまな疾患にかかりにくく、かかっても重症化のリスクを下げて、治りやすくする効果があります。
自然免疫の働きを高めるためには、規則的な生活や栄養バランスの良い食事、適度な運動や質の良い睡眠などが大切といわれています。
【配食のふれ愛】では、栄養バランスの良いメニューをご提供しています。ただいま無料試食キャンペーン中です。ぜひご利用ください。
https://www.h-fureai.com/trial/
 まごころ弁当
まごころ弁当 配食のふれ愛
配食のふれ愛 宅食ライフ
宅食ライフ すくすく弁当
すくすく弁当 まごころケア食
まごころケア食 ライフミール
ライフミール わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん 運営会社
運営会社 こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ