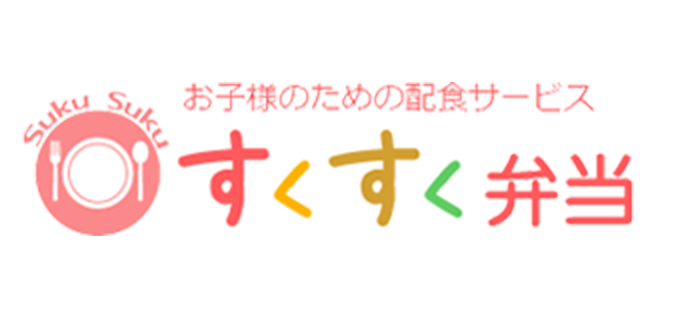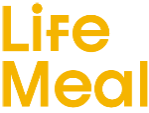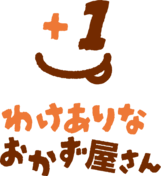こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!

腸閉塞とは、腸管の内容が何らかの原因により流れなくなってしまう病気です。
原因は様々ですが、60%は胃や大腸等の手術をしたことがあることで腸管が癒着(本来は離れている組織が損傷から回復する過程で正しくない組織とくっついてしまう現象)してしまうことで起こります。
一度腸閉塞になってしまうと、再発しやすいため、食べる物や食べ方に注意をする必要があります。ここでは、腸閉塞の治療法や予方法について解説します。
目次
腸閉塞とは?
腸閉塞は、様々な原因で小腸や大腸に内容物が詰まってしまう病気です。イレウスとも呼ばれています。
腸閉塞では、内容物が通過出来ずに溜まっていくため、お腹の痛みや張り、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。時には緊急手術が必要になることもある病気です。
胃や腸、産婦人科系などお腹の手術をした方は腸閉塞になりやすく、その確率は50~90%とも言われています。
多くは術後当日から1~2週間で癒着が始まり、数ヶ月~2~3年後に腸閉塞となることがありますが、稀に10年以上経ってから発症する方もいます。
近年では術後管理は進化しているため、重症化することは少なくなっていますが、時には命に関わることもあるため、症状を見逃さずに早期に治療を開始することが大切です。
また、腸閉塞は繰り返して発症してしまうことが多く、腸閉塞の治療を受ける度に再発しやすくなる、という特徴があります。
腸閉塞の症状は?
腸閉塞の主な症状は、腹痛やお腹の張り、排便・排ガスの停止、嘔吐です。
腸閉塞の原因によっては症状がみられない方もいますが、後に紹介する複雑性(絞扼性)腸閉塞の場合には発症が急激で強い腹痛が伴います。
また、熱が出たり、顔面蒼白、脈が速くなるなどのショック症状が早期からみられることもあり、命に関わる危険な状態となることもあります。
単純性(閉塞性)腸閉塞の場合には、痛みは持続的ではなく、波があることが典型的です。
腸閉塞の原因は?
腸閉塞は原因によって以下のように分類されます。
◇機械的腸閉塞
物理的に腸が閉塞することで起こる腸閉塞です。腸閉塞の原因の90%はこの機械的腸閉塞だと言われています。
・単純性(閉塞性腸閉塞):癒着や腫瘍などにより腸の内腔が閉塞して起こる
・複雑性(絞扼性腸閉塞):腸捻転や鼠径ヘルニア嵌頓などで腸がねじれたり、血行を障害されることで起こる
◇機能的腸閉塞
腸管の運動が停止して起こる腸閉塞です。
・麻痺性腸閉塞:腸の動きが麻痺して起こる
・痙攣性腸閉塞:腸の一部が痙攣して起こる
物理的に腸が閉塞する単純性(閉塞性)腸閉塞では、お腹の手術歴が原因となることが多いです。
手術をすると、傷が治っていく過程で癒着といって他の組織や臓器の表面とくっついてしまうことがあります。
癒着により腸管が閉塞してしまうことで腸閉塞となってしまうのです。
大規模なお腹の手術ほど癒着を起こしやすく、特にがんの患者には癒着が多くなる傾向があることが分かっています。
また、消化管に穴が開く病気(消化管穿孔)や虫垂炎、胆嚢炎などの既往がある場合にも、腹膜の癒着による腸閉塞を起こす可能性があります。
腸の一部がねじれることで起こる複雑性(絞扼性)腸閉塞では、寝たきりの高齢者や慢性的な便秘、薬物の影響などでS状結腸が弛み、ねじれてしまうことで起こります。
さらに鼠径ヘルニアといって、腸管の一部が足の付け根からはみ出る病気も腸が閉塞する原因となります。
鼠径ヘルニアを治療せず放置していると、腸が周囲の筋肉で締め付けられてしまい、押しても腸が元の位置に戻らなくなってしまうことがあり(嵌頓状態)、腸閉塞となることがあります。
はみ出た部分の血流が途絶えてしまうため、非常に危険な状態です。
腸が閉塞していないのに、腸の運動が停止してしまい、内容物が流れなくなる麻痺性腸閉塞では、感染性腸炎や腹膜炎、お腹の手術歴、薬の副作用などで腸管が麻痺してしまうことが原因で起こります。
腸管の一部が痙攣することで起こる痙攣性腸閉塞は頻度は少ないですが、虫垂炎や胆石症、腎結石の発作時、お腹の打撲や鉛中毒などが原因となります。
Q.なぜ手術のあとに癒着が起こるの?
A. 体の正常な反応によるためです。
手術で切開したり電気メスで止血したりすることで組織の損傷が起きると、損傷した組織は、皮膚に傷を負った時にだんだんかさぶたができてくるのと同じように治癒していきます。
人間の体の中では組織と組織の間は結合組織で繋がっており、損傷を受け治癒する過程の組織Aと隣り合って同様に損傷を受けた組織Bがある場合、傷ついた組織Aを塞ぐために必要な細胞が組織AとBの間を迷走するのです。
これは手術直後から始まります。術後3日を経過したあたりから、組織Aと組織Bの損傷した箇所には両方を繋ぐ新しいコラーゲンや血管、神経芽細胞が出来始め、徐々に組織同士がくっついていきます。
これが癒着現象のおおまかな流れです。
癒着は手術以外でも、出血や感染といった炎症反応によって引き起こされます。くっついてしまった組織同士の繋がりは強固であるため、剥がすのが難しくなります。
最近ではほとんどの手術で、できるだけ癒着が起こらないよう手術中に予防策が講じられています。
また、かつては手術後何日間かベッド上で安静を保っていましたが、癒着を予防するためにも術後はなるべく早期に離床して歩くことが推奨されています。
腸閉塞の治療方法は?
腸閉塞は自然治癒することはほとんどありません。腸閉塞を発症した場合には基本的に入院して治療をすることとなります。
閉塞が軽度の場合には手術は行わずに、保存療法が適用となります。保存療法では、食事や飲水を中止して腸を休ませ、チューブを鼻から、もしくは肛門から腸まで挿入します。
チューブを鼻や肛門から挿入するのは、腸の中で詰まって先に進まなかった内容物をチューブを介して体外へ流出させ、腸の中を減圧させるためです。
減圧により腸管の腫れが治まると、閉塞状態が改善します。絶飲食の間は脱水状態とならないよう点滴で水分や栄養を補給します。
保存療法を継続しても効果がない場合、または複雑性腸閉塞である場合には腸の血流が遮断され壊死してしまう危険性があるため、手術の適応となります。
単純性腸閉塞の場合には閉塞の原因が腫瘍であれば腫瘍を取り除いたり、癒着が原因であれば癒着している部分を剥がす、もしくは腸管の損傷具合を見て切除することもあります。
複雑性腸閉塞では腸管がねじれたり、はみ出たりして血流が遮断されている部分を修復します。
腸管が壊死してしまっている場合は、一度壊死した腸管は元には戻らないため切除する必要があります。
腸閉塞を予防するための方法とは?
腸閉塞を予防するためには食事が大事なポイントです。お腹の手術歴があると、術後数年経過していても腸閉塞を発症することがあります。
食事に注意していても完全に防ぐことはできませんが、できるだけ腸閉塞を起こさないように工夫することが必要となります。
腸の手術をした場合には、手術の程度(腸管の切除の有無、切除部位や範囲)などによっても食事のすすめ方が異なりますので、食事の形態や食べても問題ない食品かどうか主治医に確認し、段階的に食事形態や食事量を上げていきましょう。
また、運動も腸閉塞予防には効果的です。体を動かすと、腸の動きも良くなります。ウォーキングなどの適度な運動を生活に取り入れてみましょう。
便秘気味の場合には、主治医に相談し、必要に応じて緩下剤や整腸薬を使って排便コントロールを行います。
腸閉塞を予防するための食事のポイント
・一度に大量に食べない
腸管が狭窄することで起こる腸閉塞では、一度に大量に食べると消化しきれずに腸が詰まってしまうことがあります。
退院後は2ヶ月ほどかけて段階的に量を増やして、1回の食事量は腹8分目程度を目安としましょう。
・早食いをしない
早食いも腸に大量に食べたものが流れ込むため詰まりやすくなる原因となります。食事はゆっくりよく噛んで食べましょう。
・手術後1~2ヶ月程度はなるべく軟らかいものを食べる
手術後は軟らかいお粥やうどんなど消化しやすいものを食べるようにしましょう。
手術後3ヶ月程度かけ体調をみながら徐々に油を使った料理や繊維質の食品など、少量ずつから食べ始めていきましょう。
・ガスが発生しやすい食品や、刺激が強い食品は控えめにする
手術後はお腹が張りやすくなったり、便通が変化しやすくなります。
そのため、ガスが発生しやすくなるにんにくや炭酸飲料、腸を刺激する香辛料やアルコールは控えめにしましょう。
・食物繊維が多い食品を多く摂らない
便秘に効果的な食物繊維ですが、お腹の手術をしている方は要注意です。繊維質は消化されにくいため、内容物が腸に詰まりやすくなってしまいます。
ごぼうやセロリ、さつまいもや山菜など繊維が多い食材は量を控えめにし、調理の際は皮や筋を取り除き、繊維を断ち切る方向に細かく切って食べるようにしましょう。
みじん切りにしてしまうと丸飲みしてしまう恐れがあるため、噛める大きさに切り、よく噛むことが大切です。
また、豆類も繊維が多く腸に詰まりやすい食品です。納豆はひき割りにしてご飯と別に食べたり、煮た大豆や枝豆は薄皮を取り除いてから食べるようにしましょう。
・便秘予防に水分をこまめに摂る
繊維質を控えると便秘になりやすくなります。水分をこまめに摂ることで便が硬くなることを防ぎ、腸の運動を促します。
・食事はバランスよく、消化吸収がしやすいものを中心に摂取する
消化の悪い食品を食べ過ぎると腸が詰まりやすくなります。消化しにくい食品は食べる量を控えめにし、細かくきざんだり、柔らかく煮込んだりなど調理法を工夫しましょう。
<食品の選び方>
| 種類 | 消化に良い食品 | 控えた方が良い食品 | |
| たんぱく質 | 肉類 | 牛赤身肉、豚赤身肉、鶏肉(皮は取り除く)、 鶏ささみ、レバーなど | 脂肪の多い肉(牛・豚バラ、ロース、霜降り肉、ベーコン)など |
| 魚類 | 白身魚、アジ、エビ、貝柱、練り製品 | いか、たこ、干物など | |
| 卵 | 鶏卵、うずらの卵 | ||
| 豆類 | 豆腐、高野豆腐、こしあん、ひき割り納豆など | 大豆、小豆、つぶあん、おから | |
| 乳製品 | 牛乳、チーズ、ヨーグルトなど | ||
| 糖質 | 穀類 | 軟飯、お粥、食パン、うどん、 マカロニ、 スパゲティなど | 玄米、赤飯、ラーメン、とうもろこしなど |
| 芋類 | じゃがいも、里芋、長芋 | さつまいも、こんにゃくなど | |
| 果物 | りんご、もも、バナナ、缶詰類など | パイナップル、みかん、柿、干し柿、ドライフルーツなど | |
| 脂質 | 油脂 | バター、マーガリン、マヨネーズ、食物油 | ラード、油の多いドレッシング、油の多い料理(揚げ物、中華料理)など |
| ビタミン ミネラル | 野菜 | 緑黄色野菜:かぼちゃ(皮なし)、人参、ほうれん草、小松菜、トマト(皮なし)など 淡色野菜:大根、キャベツ、レタス、きゅうり、玉ねぎ、なす(皮なし)、かぶ、白菜など | 硬い繊維の野菜(ごぼう、たけのこ、レンコン、山菜、セロリなど) きのこ類、漬物など |
| 海藻 | のり佃煮 | わかめ、昆布、ひじきなど | |
| その他 | 飲料 ・ 菓子 | ビスケット、ゼリー、プリン、カステラ、米菓子、ウエハースなど | アルコール飲料・炭酸飲料・コーヒーなど 揚げ菓子、チョコレート、生クリームの多いケーキなど |
Q.腸閉塞に、乾燥わかめでなるって本当?
A.そのようなケースが確認されています。
稀ですが、食べ物が詰まることで腸閉塞を発症することがあります。
乾燥わかめは重量比でおよそ10倍以上膨らみます。
低カロリーでダイエットに適している食材ですが、だからといって食べすぎてしまうと、わかめの膨張に消化が追い付かず、腸に詰まってしまうことで腸閉塞となる場合があります。
乾燥わかめの食べ過ぎで救急搬送された例もあり、開腹手術でわかめを取り除く羽目になってしまった人もいます。おやつ代わりに乾燥わかめをそのまま食べることは健康な人であってもおすすめしません。
また、椎茸を丸飲みしてしまったことで腸閉塞となった事例もあります。
食べ物が詰まることで起こる腸閉塞は「食餌性腸閉塞」といい。乾燥わかめや椎茸などのきのこ類のほかにも糸こんにゃくや昆布、餅などの消化されにくいものや水分を含むと膨らむものが原因とされています。
宅配弁当を活用しよう!
腸閉塞を予防するためには日頃から食事について注意する必要があります。特にお腹の手術をしたことのある方は、消化しにくい食べ物は避け、よく噛んで食べることが大切です。
高齢者向け配食サービス「配食のふれ愛」には様々な種類のお弁当が用意されています。
配食サービスは、買い物や調理する手間をはぶくだけでなく、不要不急の外出を避けることもできる今の時代に合ったサービスです。
安否確認も兼ねているので、遠方に住んでいるご家族の安心にも繋がります。
今なら2食まで無料で試食することができます。この機会にぜひお試しください。
参考:日本消化器外科学会 イレウスの治療と予防
https://www.jsgs.or.jp/cgi-html/edudb/pdf/20101065.pdf
 まごころ弁当
まごころ弁当  配食のふれ愛
配食のふれ愛  宅食ライフ
宅食ライフ  すくすく弁当
すくすく弁当  まごころケア食
まごころケア食  ライフミール
ライフミール  わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん  運営会社
運営会社  こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ