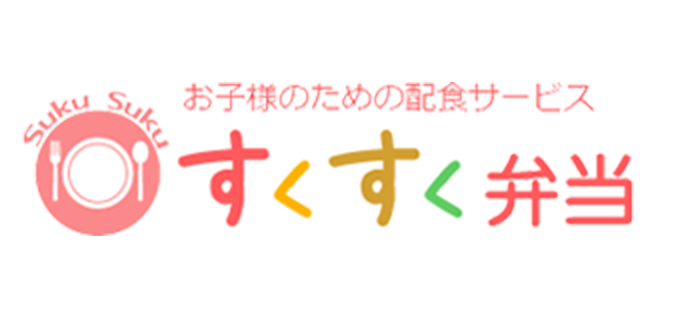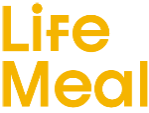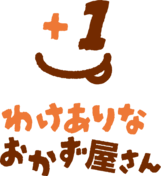こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!
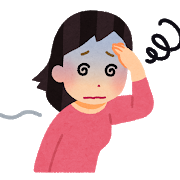
めまいは男性よりも女性に多くおこる症状といわれます。
めまいの原疾患は耳や脳にあることが多いですが、近年では寿命が延びたことにより、高齢者特有の原因によるめまいも増加しているといわれています。
目次
めまいの種類
めまいは一瞬で治まることもあれば、長時間続く場合もあります。
「突然目の前がグルグル回る」「床がやわらかくなったように足もとがふわふわする」など、めまいの感じ方にも個人差はありますが、めまいの症状は大きく3つに分けられます。
回転性めまい
天井や景色がグルグルと回っているように見えたり、自分が回っているように感じたりするめまいは、回転性めまいと呼ばれます。
急に強い症状があらわれることが多く、立っていられなくなったり、吐き気や嘔吐があることもあります。
回転性めまいがおこっているときには、眼が周期的に素早く動く「眼振」という症状が表れることがあります。
主に内耳や脳幹と小脳、内耳と脳幹、小脳をつなぐ神経路に原因があることで発生します。
浮動性めまい・動揺性めまい
地に足が付かないような、トランポリンの上を歩くようなふわふわした感覚の浮動性めまいや、足元がふらふらして地面が揺れているような感覚の動揺性めまいは、両耳の内耳の異常や脳の障害によっておこる症状と考えられます。
また高血圧やうつ病が原因のこともあります。立っていられないほどの強いめまいではなくても、長時間続くことがあります。
立ちくらみのようなめまい(眼前暗黒感)
急に起き上がったり、立ち上がったりしたときにくらっとしたり、一瞬目の前が真っ暗になるような感覚のめまいは、耳や脳の異常ではなく、脳への血流が一時的に不足することで起こる症状です。
貧血や血圧の変化、自律神経のバランスの乱れなどが原因と考えられます。
耳が原因のめまい
耳が原因のめまいでは、めまいと同時に耳鳴りや難聴、耳閉感(耳がつまったような感覚)が生じることがあります。
良性発作性頭位めまい症(BPPV)
起き上がるときや寝返りを打ったときなど、頭を動かしたときにめまいがおこります。めまいは1分以内で治まることがほとんどですが、頭を動かすたびに繰り返すことがあります。
中高年以降の女性に多く、高齢化に伴って患者数は増加の傾向にあります。
良性発作性頭位めまい症は、耳の奥にあるバランスを感知する「前庭」という感覚に異常が生じることで発症します。
前庭には回転運動を感知する三半規管と、傾きを感知する耳石器があり、耳石器には耳石というカルシウムの粒が数百個付着しています。
この耳石が何らかの理由で剥がれ落ち、三半規管に入り込むことでめまいがおこります。
耳石がはがれる理由はわかっていませんが、いつも同じ向きで頭を横にする姿勢の多い人が発症しやすいといわれます。
また中高年以降の女性に多いため、加齢に伴うホルモンバランスの変化や、骨粗しょう症とも関係があると考えられています。
医療機関では、めまいのおこる状況や眼振の有無、他症状の有無などを調べます。
ベッドに横になった状態で頭位を変えて眼振の症状を確認する頭位眼振検査や、特殊なメガネをかけて症状を調べる検査などを行います。
他の病気の可能性を確認するためにMRIやCT検査が行われることもあります。
三半規管から耳石が出ればめまいは治るので、耳石が自然に耳石器に戻り、数週間でめまいが治まることもあります。
治療は医師が頭をゆっくりと動かして三半規管にたまっている耳石を出す「頭位治療」や、自分でも行える「寝返り体操」もあります。一般的には薬物治療は行われないことが多いようです。
NHK健康チャンネルのサイトです。寝返り体操を動画で見ることができます。ご参考ください。
https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_592.html
メニエール病
メニエール病は内耳にあるリンパ液の量が過剰になることでおこると考えられていますが、その原因ははっきりわかっていません。
発作的に強い回転性のめまいがおきて、数分から数時間も続くこともあります。変動のある低周波の軟調や、耳鳴りも特徴的な症状で、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。
40歳以降に発症することが多く、発作を繰り返すことで聴力が低下することがあります。
治療は薬物療法が中心ですが、ストレスや疲労の蓄積が発作を誘発するといわれます。日常生活では無理をせず、規則的な生活を心がけましょう。
塩分、アルコール、カフェインの摂取を控えた栄養バランスの良い食事と、十分な睡眠も大切です。
内耳炎
内耳に炎症が起きることが原因でめまいがおきることがあります。
急激に内耳に炎症が及んだ場合は、激しい回転性のめまいに加えて吐き気や耳鳴り、眼振、難聴などの症状があらわれます。
慢性中耳炎から徐々に内耳へと炎症が及んだ場合には、軽いめまいや耳鳴りの症状が徐々に進行します。
治療は主に抗菌薬の処方や鼓膜切開術により中耳から液体を排出する処置が行われることがあります。状態によっては、耳の後ろ広範囲に手術が必要なこともあります。
前庭神経炎
風邪の症状から1~2週間後に、突然の回転性のめまいがおこるのが前庭神経炎です。めまいの中でも非常に強い症状ですが、耳鳴りなどはなく、聴力に影響はありません。
めまいは比較的すぐに、数日で消失することが多いようですが、めまいがしているような感覚は数か月残ることがあります。
原因ははっきりとわかっていないことも多く、風邪症状のあとにおこることから、アレルギー反応やウイルスが関係しているのではないかと考えられています。
治療はめまいを抑える薬や嘔吐を抑える薬、ステロイド剤などが処方されることがあります。
脳が原因のめまい
脳が原因のめまいでは、耳鳴りや難聴、耳閉感を伴うことはあまりありません。
脳から生じるめまいは非常に強い、今まで経験したことがないようなめまいのことが多く、顔や手足のしびれやふるえ、物が二重に見える、力が入らない、言葉が出ないなどの症状を伴います。
脳卒中(脳梗塞・脳出血)
脳卒中によって平衡感覚の経路のどこかで障害がおきると、めまいがおこります。
脳卒中によるめまいは数十分から数時間と長く続くのが特徴で、同時に「ろれつが回らない」「手足に力が入らない」「ものが二重に見える」「感覚がおかしい」などの症状があります。
めまいの症状や程度は脳の梗塞部分や出血部分によって異なりますが、前記の他にも頭痛や頭重感、嘔気や嘔吐が強い場合はすぐに受診をしましょう。
また耳が原因のめまいの既往がある場合、数年内に脳卒中を起こすことがあります。耳が原因のめまいを脳卒中の警告ととらえて脳の検査をしておくと、脳卒中の予防となることがあります。
てんかん
てんかんは、脳の神経細胞が過剰な電気的刺激によって異常な興奮をすることで発作がおこる病気です。
てんかん発作にはさまざまな症状がありますが、めまいもそのひとつです。てんかんは子供の頃に発症する場合が多いのですが、現在は高齢者のてんかん発症率も上昇しています。
高齢者のてんかんは、脳卒中の後遺症や加齢に伴う脳の異常、認知症なども関係しているといわれます。
その他の原因のめまい
気圧変化
気圧の変化によっておこるめまいや頭痛などの不快症状を気象病と呼びます。
季節の変わり目や台風などの影響によってめまいや耳鳴り、頭痛などの症状が悪化することがあります。
低気圧によるめまいは、体内の水分バランスが乱れて体内に余分な水分が溜まり、血管拡張や自律神経の乱れを引きおこしたり、内耳が気圧差の影響を受けやすいためにおこると考えられます。
内耳と自律神経には深いかかわりがあると考えられており、普段から内耳の血流を良くしておくことで、気象病の予防や改善に効果があるといわれます。
両耳をつまんで、上下に引っ張ったり、前後に回したりするマッサージが有効といわれます。
貧血
貧血が進行するとめまいがおこることがあります。
耳や脳に異常がない仮性めまいであれば貧血が治ればめまいは解消しますが、鉄欠乏性貧血だけではなく、他の疾患や体内で出血を伴う疾患などが疑われることもあります。
めまいの他に、息切れや強い疲労感、不眠や食欲低下、手足の冷感などがある場合は、医療機関を受診しましょう。
更年期障害
更年期とは閉経前後のおよそ5年間を指し、更年期にあらわれる、他の疾患を伴わない不快症状を更年期障害と呼びます。
その更年期障害の症状のひとつにめまいがありますが、更年期障害のめまいについてははっきりわかっていないことも多く、必ずしも女性ホルモンの低下によってめまいがおこりやすいというわけではないようです。
主な原因は自律神経の乱れによるもので、疲労や睡眠不足、ストレスなどが引き金となっておこると考えられています。
熱中症
熱中症の初期症状にめまいがあります。夏季の猛暑日などにめまいを感じた場合は、すぐに日陰や屋内の涼しい場所に移動し、着衣を緩めて水分を摂りましょう。
氷や保冷剤等がある場合は、首・わきの下・足の付け根を冷やします。
軽いめまいの時点で適切な対処ができれば、重症の熱中症は回避できることがほとんどですが、しばらく休んでもめまいが治まらなかったり、水分が摂れない、頭痛や吐き気がするなどの場合には、医療機関を受診しましょう。
左右の視力差
左右の視力の差が大きい場合に、回転性のめまいがおこることがあります。
白内障などの手術後や、メガネが合わなくなったためにおこることもあります。メガネやコンタクトレンズを使用している場合は、定期的に視力をチェックし、適正に調整しておくようにしましょう。
低血圧
血圧が下がり過ぎるとフラフラとしためまいを感じることがあります。
血圧は心臓から出た血液を全身に運ぶために必要な圧力なので、血圧が低すぎると臓器に届く血流量が減少する可能性があります。
通常は多少血圧が下がっても、脳への血流量が減少しないように調整されていますが、過度に血圧が下がると脳への血流量が減少して酸素が不足し、平衡中枢が正常に働かなくなって、めまいが出現します。
高血圧症で降圧剤を服用している場合に、薬の作用によって血圧が下がり過ぎる可能性もあるので、その場合はかかりつけの医師に相談して降圧剤を調整したり、薬を変更することでめまいは消失します。
心因性のめまい
耳にも脳にも異常がなく、原因が特定できない場合に「心因性めまい」とされることがあります。
精神的なストレスや自律神経の乱れが内耳や脳幹の機能に悪影響を及ぼして発症すると考えられています。
原因となるストレスを取り除ければ、めまいの症状は治るはずですが、めまいの症状が強く生活に支障をきたすような場合や、症状が長く続く場合は心療内科を受診しましょう。
めまいは不眠や頭重感と並び、うつ病の三大症状といわれています。
うつ病によるめまいは、抗不安剤や抗うつ剤などで改善されることが多いのですが、うつ病がめまいをひきおこすメカニズムはまだ詳しくわかっていません。
高齢者に多いめまい
高齢者はめまいをおこしやすいといわれます。その原因は必ずしも耳や脳の疾患が原因とは限らず、検査をしても原因がよくわからないこともあります。
しかし、めまいが頻回になると思うように外出ができなくなり、大きく生活の質の低下を招きます。
また、めまいによって転倒し骨折すると、そのまま歩くことが困難になる可能性もあります。高齢者のめまいには次のような要因が挙げられます。
平衡感覚の低下(加齢性平衡障害)
体の平衡を保つためには、「目で見た情報」「重力や加速、回転などを感知した耳からの情報」「自分の体の動きを感知する足の裏の感覚」などの情報を小脳が統合して体のバランスをとることが必要です。
高齢者では視力の低下、内耳や前庭神経の働きの低下、足の裏の感覚の鈍化などの要因が重なり合い、明らかな疾患がなくても平衡感覚のバランスを保つために必要な情報処理が速やかにできずに、めまいをおこしやすくなると考えられます。
血圧変動
加齢とともに血圧を調節する能力が低下し、血圧の変動が激しくなることがあります。
血圧の急上昇や急降下によって脳に酸素や栄養が十分に供給されなくなり、めまいをおこしやすくなると考えられます。
薬の副作用
高齢者は高血圧や糖尿病の他、さまざまな疾患を持っていることが多く、治療のために薬も複数服用していることがあります。
薬の中には、めまいが副作用に挙げられているものも多くあるため、めまいの原因となっている可能性もあります。
前庭神経の圧迫
加齢によって動脈硬化がおこると、動脈が延長して蛇行するようになります。
そのため前庭神経が圧迫されて、耳鳴りとめまいの症状をおこします。治療は抗けいれん薬を投与したり、手術で血管と神経の間にスポンジを挟むことで完治する可能性があります。
めまいがおきたときの対処と予防法
前述のように、脳卒中など脳の疾患が原因でおこるめまいの中には、命にかかわる場合もあります。
めまいの他にも次のような症状があるときは、すぐに医療機関を受診するか救急車を呼びましょう。
・顔や手足にしびれがある。
・ろれつが回らない、言葉が思うように出てこない。
・物が二重に見える
・激しい頭痛や吐き気がある。 など
めまいやこれらの症状が比較的軽い場合でも、ひとりで受診に向かったり、自分で車を運転するようなことは止めましょう。途中で再発作がおきたり、事故につながる恐れがあります。
医療機関を受診するときは誰かに連れて行ってもらうか、救急車を要請してください。
これらの症状がない場合や、原因がわかっているめまいの場合には、次のような対処をしましょう。
ゆっくりと安静にする
めまいがおきたときにはまず落ち着いて、いったんその場で安静にしましょう。
歩いているときは止まる、立っている場合は座るなどして、急激な症状が落ち着いてから、休めるような場所へゆっくり移動します。
めまいが強く動けない場合は、無理せず周囲の人に助けを求めましょう。
また車の運転中にめまいがおきた場合は、車のスピードをゆっくりと落としてハザードランプをつけ、車を路肩に寄せて止めて休みましょう。
横になって休める場合は静かな場所を選んで横になり、眼を閉じて外からの刺激を少なくします。照明は暗くして、テレビや音楽などは止めて静かに休みましょう。
ビタミンB群を積極的に摂る
ビタミンB12は神経の代謝にかかわっていて、めまいの治療薬として処方されることもあります。また睡眠のリズムを整える働きもあるといわれます。
ビタミンB1にも脳の働きを適正に保つ働きがあるので、めまいの予防には有効といわれます。
ビタミンBにはB1、B2、B6、B12、その他にも仲間が数種あり、お互いが協力し合って働くため、単体で摂るよりもビタミンB群として摂ることが大切です。
ビタミンB群は体内にためておくことができないため、毎日の食事からこまめに摂る必要があります。ビタミンB群は比較的いろいろな食べ物に含まれているので、バランスよく食べるように心がけましょう。
ビタミンB群を多く含む食べ物
| 種類 | 主な働き | 多く含む食べ物 |
| ビタミンB1 | 糖質の代謝にかかわる補酵素 | 豚ヒレ、豚もも、そば、など |
| ビタミンB2 | 脂質の代謝にかかわる補酵素 | 豚レバー、うなぎ、ブリ 鰆、モロヘイヤ、牛乳、など |
| ビタミンB6 | アミノ酸の再合成を助ける補酵素 | カツオ、マグロ、鮭、豚ヒレ バナナ、さつま芋、玄米、など |
| ビタミンB12 | タンパク質合成、アミノ酸の代謝 正常な赤血球の生成 | 牡蠣、あさり、さば、ほたて ホッケ、しじみ、など |
| ナイアシン | エネルギー代謝にかかわり、補酵素の働きを助ける。ビタミンB1・B6と助け合って働く | たらこ、マグロ赤身、鶏むね サバ、鶏ささみ、とうもろこし、など |
| パントテン酸 | 善玉コレステロールを増やす ホルモンや抗体を産生する | 鶏レバー、鶏ささみ、納豆 アボカド、など |
| 葉酸 | 正常な赤血球の生成を助ける | 鶏レバー、菜の花、モロヘイヤ ほうれん草、ブロッコリー、など |
| ビオチン | 脂質・糖質・たんぱく質の代謝にかかわり、皮膚の機能を保持する | 酵母、きのこ類、など |
ビタミンCを積極的に摂る
ストレスは、めまいを誘発したり、めまいの症状を悪化させる可能性があります。
ビタミンCは抗ストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾール」の材料のひとつとなります。ビタミンCは人の体内で合成できないため、食べ物から摂取する必要があります。
また、体内にためておくことができないため、毎日摂るように心がけましょう。
【配食のふれ愛】では、栄養バランスの良いメニューをご提供しています。忙しいときでも、電子レンジで温めるだけで栄養バランスの良いお食事を摂ることができます。ただいま無料試食キャンペーン中です。ぜひご利用ください。
https://www.h-fureai.com/trial/
カフェインを控える
カフェインには神経を興奮させる働きがあり、めまいの誘因になったり悪化させたりする可能性があります。コーヒーや紅茶、その他のお茶類の飲み過ぎには注意しましょう。
カフェインは栄養ドリンク剤や、エナジードリンクと呼ばれる清涼飲料水にも多く含まれていることがあるため、注意しましょう。
生活のリズムを整える
めまいと自律神経のバランスは深いかかわりがあります。規則的な生活を心がけ、十分な睡眠をとって過労を避けましょう。
バランスの良い食生活と無理のない運動、ストレスをうまく解消することも大切です。
めまいに効くツボ
脳が酸欠状態になったときにめまいがおきることがあります。耳の外側(縁)の交感神経の求心性線維を刺激することで脳の血流が促進され、めまいが治まることがあります。
初めに耳たぶから耳の縁に沿って上に向かって、親指と人差し指で挟み、優しくもみほぐしましょう。深呼吸しながら心地よいと感じる程度に行います。
・翳風(えいふう)
翳風は、耳たぶの裏側、あごの付け根にある多くなくぼみにあるツボです。人差し指でじわじわと押し、ゆっくと戻すを繰り返します。
・風池(ふうち)
風池は、首の後ろの太い筋の外側、生え際にあるくぼみにあるツボです。人差し指、中指、薬指の3本で円を描くようにもみほぐします。
・聴耳(ちょうきゅう)、聴会(ちょうえ)
聴耳は、耳の前、もみあげのところで、口を軽く開けたときにできるくぼみにあるツボで、聴会はそのすぐ下にあります。
聴耳に中指をあて、人差し指を並べて2本の指でじわじわと押し、ゆっくと戻すを繰り返します。
いずれのツボも、ゆっくりとした動作で、心地よいと感じる程度に行いましょう。強く刺激したり、長時間続けることは控えましょう。
めまいに効く漢方薬
漢方では症状だけではなく、人の心身全体を診ます。体の不調は、体を構成する3つの要素である「気・血・水」のバランスの乱れが原因と考え、そのバランスを整えるという考え方をします。
漢方薬は、原因がはっきりとしない体の不調にも効くと考えられています。
・苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
体力がなく、めまい、ふらつき、のぼせ、動悸などがあって、尿量が減少している人に用いられる処方です。
そうした症状のある人の神経症、立ちくらみ、めまい、頭痛、息切れなどに効きます。
・半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)
胃腸機能の虚弱によって冷えのある気虚の人のめまいや、めまいで吐き気が誘発されている場合に効く漢方薬です。
・五苓散(ごれいさん)
五苓散はさまざまな疾患に幅広く使われる漢方薬です。浮腫など水の滞りの症状がある場合のめまいに効く漢方薬です。
漢方薬は症状と体質などを総合的に診て処方がされます。いろいろな対策や治療に効果が感じられない場合には、かかりつけの医師に相談してみましょう。
漢方薬は比較的副作用が少ないといわれ、ドラッグストアなどで購入できるものも多くなっていますが、特に服用中の薬がある場合は、かかりつけの医師や薬剤師に相談してから利用するようにしましょう。
まとめ
めまいの原因はさまざまで、自然に治ってしまうこともあれば、命にかかわる重大な症状としてあらわれることもあります。
しかし、めまいの原因がわかれば適切な対処をとることもできるので、めまいの症状がつらい場合は自己判断せずに、医療機関を受診しましょう。
 まごころ弁当
まごころ弁当  配食のふれ愛
配食のふれ愛  宅食ライフ
宅食ライフ  すくすく弁当
すくすく弁当  まごころケア食
まごころケア食  ライフミール
ライフミール  わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん  運営会社
運営会社  こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ