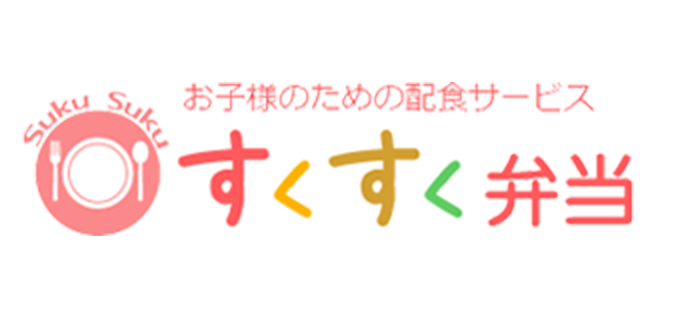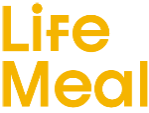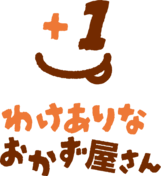こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!

高齢になると、入れ歯が合わないことや栄養不足、さまざまな病気の影響により口内炎ができやくなります。
口内炎ができると食べ物により口内が刺激され痛みが増すため、食べる意欲が低下することもあります。
ここでは口内炎ができる原因や口内炎ができた時の食事の摂取方法、予防に効果的な食べ物などについて解説していきます。
目次
口内炎はどうしてできるの?
口内炎とは口の中の粘膜に起こる炎症のことです。ひとくくりに口内炎といっても腫れや痛み、出血、ただれなど軽度から重症なものまで様々な症状がみられます。
口内炎ができる原因は明確にはなっていませんが、睡眠不足や栄養不足、ストレスなどが考えられています。
他にも口の中を噛む癖があったり、高齢者では入れ歯が合わずに口の中の粘膜が傷ついたりすることが原因となり口内炎ができることもあります。
また、病気の症状の一つとして口内炎ができる場合や、化学療法・放射線療法を受けている場合の副作用として起こることがあります。
化学療法とは抗がん剤治療のことで、薬の直接的な作用と免疫力の低下による細菌感染などにより30~40%の人に口内炎が発生する頻度が高い副作用です。
放射線療法による口内炎は口や耳、のどに放射線を照射している場合に唾液を出す細胞が傷つけられて唾液が減少することにより細菌が繁殖しやすくなってできる場合があります。
また、放射線療法の副作用である免疫力の低下も口内炎ができやすくなる原因の1つです。
口内炎の種類
・アフタ性口内炎
口内炎の中で最も多いのが、アフタ性口内炎です。
原因は明確にはなっていませんが、ストレスや疲れ、睡眠不足などによる免疫力の低下やビタミンB2の不足などが関与していると考えられています。
アフタ性口内炎では、赤いふちの丸くて白い潰瘍が頬や唇の裏側、舌、歯茎にできます。
大きさは2~10mm程度で、通常10日から2週間ほどで自然治癒し跡は残りません。
なかなか治らないときや何度も再発するときはベーチェット病などの病気が隠れている場合や、薬による副作用が原因となっている場合もあるため、医師の診察を受けることをおすすめします。
・カタル性口内炎
カタル性口内炎は入れ歯が合わずに頬に接触したり、口の中を噛んでしまったりすることで傷の部分に細菌が繁殖することで起こる口内炎です。
口の中をヤケドしてしまうことや、薬品による刺激で生じることがあります。
アフタ性とは違い、境界が不明瞭で口の中の粘膜が赤く腫れることや、水ぶくれができることが特徴です。
唾液の量が増えて口臭が発生することもあります。また、食べたものの味が分かりにくくなる場合もあります。
・ウイルス性口内炎
唇にできるヘルペスも口内炎の一種です。ヘルペスは単純ヘルペスウイルスの感染によって起こります。
主に唾液などの接触感染やくしゃみや咳などによる飛沫感染が原因です。
他にも梅毒やクラミジアなどの性感染症が原因で起こるウイルス性口内炎もあります。
また、もともと口の中にいるカンジダ菌は、免疫力が低下すると菌が増殖して口内炎を発症することがあります。
ウイルス性口内炎では口の中の粘膜に複数の小さな水ぶくれを形成します。そのため、破れると強い痛みを生じたり、発熱がみられたりすることもあります。
・その他の口内炎
アレルギーが原因で起こるアレルギー性口内炎や、タバコによる熱で生じるニコチン性口内炎などがあります。
ニコチン性口内炎はがん化する可能性もあるため、喫煙を習慣としている人は注意が必要です。
口内炎を早く治す方法・予防する方法
・口の中を清潔を保つ
→口の中を清潔に保つことで菌が繁殖しにくくなるため、口内炎を予防して重症化を防ぐことができます。
殺菌・消毒効果のあるうがい薬を使うと効果的です。うがいの回数は 起床時、毎食前後、就寝時などに1日 7~8 回が目安とされています。
ただし、うがいだけでは限界があるため、歯磨きを行うことが大切です。
回数は毎食後、 寝る前の 1 日 4 回が推奨されており、食事をしていなくても、歯垢は歯に付着するので 1 日 1 回は必ず歯磨きをしましょう。
歯ブラシは軟毛か超軟毛で、動かしやすい小さめのものがおすすめです。
歯磨き粉はメントールやアルコールが含まれない低刺激性のものを使用しましょう。
口内炎がある部分が傷つくと治りが遅くなるため、口内炎に歯ブラシが当たらないよう注意しましょう。
入れ歯がある場合には、毎食後に口をすすぎ、少なくとも1日2回は柔らかいブラシでブラッシングを行うことが推奨されています。
入れ歯は寝ている間は外し、清潔にして密閉容器に保管します。
<効果的な歯磨きの方法>
歯ブラシは毛先を歯に垂直に押し当てて、横に細かく振動させるように動かします。
大きく動かすとあまり汚れが取れないばかりか、歯肉を傷つけて歯の表面をすり減らす危険性があります。
歯ブラシの届きにくい歯と歯の間には、歯間ブラシなどを使いましょう。
・口の中の保湿をする
口の中が乾燥していると菌が繁殖しやすくなります。
唾液の量が不足している場合には水でこまめに口をすすいだり、市販のスプレーやジェルなどを使ったりして保湿を心がけましょう。
・禁煙をする
タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させる作用があり、局所の血液の供給量が減少します。
そのため、喫煙すると少しのきっかけで口の中が傷つきやすくなったり、傷の治りが遅くなったります。
さらに口の中が乾燥しやすくなり、細菌が繁殖しやすい口腔環境となります。
・口内炎治療薬を使う
口内炎に効く軟膏や、パッチタイプの薬が市販されています。
直接患部の炎症を鎮めるだけでなく、局所麻酔薬が配合されており、使うと一時的に痛みが減弱するものもあります。
・低出力レーザー
低出力のレーザーによる口内炎治療を行うことができる医療機関があります。
低出力レーザーは細胞の活性化やコラーゲン新生の促進、血流改善や血管新生を促進し、痛みの緩和や治癒の促進効果があります。
・規則的な生活をして免疫力を高める
睡眠不足の状態が続くと新陳代謝の速度の低下や、身体の抵抗力が弱まる原因となります。
これにより口の中の粘膜が荒れやすくなったり、菌が繁殖しやすくなったりすることから、睡眠を十分にとり、疲労を溜めないようにしましょう。
・ビタミンを十分に摂る
口内炎を早く治すためには、ビタミンを十分に摂取することが大切です。
特に、皮膚や粘膜を修復する効果のあるビタミンC、B2、B6、葉酸は積極的に摂りましょう。
口内炎の予防に効果的な食べ物とは?
・ビタミンC
コラーゲンの合成により、皮膚や粘膜、毛細血管を正常に保ち、出血を防止する働きがあります。免疫力を高める働きもあります。
ビタミンCは水溶性ビタミンであり、水に溶けやすく、酸化しやすいという特徴があります。
そのため、調理をせず生のまま食べるとより多くのビタミンCを摂取することができます。
また、ビタミンCは排泄されるまでの時間が短いため、こまめに摂取する事が大切です。
<ビタミンCが多く含まれる食材>
| 食品名 | 目安量 | 目安量あたりの含有量(mg) |
| オレンジ | 小1/2個(80g) | 48 |
| いちご | 5粒(75g) | 46.5 |
| パイナップル | 1/8切れ(160g) | 43.2 |
| キウイフルーツ | 1/2個(60g) | 41.4 |
| 赤ピーマン | 1/4個(20g) | 34 |
| カリフラワー | 2房(40g) | 32.4 |
| 黄ピーマン | 1/4個(20g) | 30 |
| グレープフルーツ | 小1/2個(80g) | 28.8 |
| かぼちゃ | 4cm角2切れ(60g) | 25.8 |
・ビタミンB2
脂肪の代謝や免疫の維持に関与しており、皮膚や粘膜を保護したり炎症を抑えたりする働きがあります。魚や卵、乳製品に多く含まれます。
<ビタミンB2が多く含まれる食材>
| 食品名 | 目安量 | 目安量あたりの含有量(mg) |
| 豚レバー | 1人前(60g) | 2.16 |
| うなぎ | 1串(100g) | 0.74 |
| モロヘイヤ | 1人前(80g) | 0.42 |
| ぶり | 1切れ(100g) | 0.36 |
| さわら | 1切れ(100g) | 0.35 |
| 牛乳 | コップ1杯(200ml) | 0.3 |
| 納豆 | 1パック(50g) | 0.28 |
| ほうれん草 | 1人前(80g) | 0.16 |
| アーモンド | 8粒(10g) | 0.11 |
・ビタミンB6
皮膚や粘膜の強化・保護をしたり、炎症を抑えたりする働きがあります。
1日に推奨されている摂取量は成人男性で1.4mg、成人女性で1.2mgですが、タンパク質の摂取量が増加するとビタミンB6の必要量も増加するため、タンパク質と一緒にビタミンB6が含まれる食品も多く摂取するようにしましょう。
<ビタミンB6が多く含まれる食材>
| 食品名 | 目安量 | 目安量あたりの含有量(mg) |
| かつお | 刺身5~6切れ(100g) | 0.85 |
| まぐろ(赤身) | 刺身5~6切れ(100g) | 0.76 |
| 鮭 | 1切れ(100g) | 0.64 |
| 豚ヒレ | 1人前(100g) | 0.54 |
| 鶏ささみ | 1人前(80g) | 0.48 |
| 鶏レバー | 1人前(60g) | 0.39 |
| バナナ | 1本(100g) | 0.38 |
| 赤パプリカ | 1/2個(80g) | 0.3 |
| さつまいも | 1/2本(100g) | 0.26 |
| 玄米 | 茶碗1杯(120g) | 0.25 |
・葉酸
赤血球を中心に新しい細胞の合成や修復を促す働きがあります。
葉酸は熱に弱く、調理中に失われやすいため、生で食べられる野菜や果物から摂取すると良いでしょう。
| 食品名 | 目安量 | 目安量あたりの含有量(μg) |
| 鶏レバー | 1人前(60g) | 780 |
| 菜の花 | 1人前(70g) | 238 |
| モロヘイヤ | 1人前(80g) | 200 |
| ほうれん草 | 1人前(80g) | 168 |
| ブロッコリー | 1人前(70g) | 147 |
| いちご | 中5個(100g) | 90 |
| 焼き海苔 | 1枚(3g) | 57 |
口内炎がある時の食事の工夫方法は?
痛みで食べられない状態が続くと栄養不足や体力の低下に繋がり、より口内炎ができやすくなったり、治りが遅くなったりしてしまう可能性があります。
口内炎がある時でも痛みを減らし食事を摂りやすくする工夫を紹介します。
・柔らかく水分の多い食事にする
柔らかい食べ物は噛むことを減らすことができるため、口の中を傷つける可能性が少なくなります。
裏ごしや、煮込み時間や茹で時間を長くするなど、柔らかく調理しましょう。
また、水分が多く含まれていると口の中でまとまりやすく飲み込みやすくなります。
ゼリー寄せにすることや、あんかけや汁にとろみをつけるなどの調理方法がおすすめです。
・口当たりが良くさっぱりした食事にする
噛むことや固形物が患部に触れると辛いときは、茶碗蒸しや冷奴、卵豆腐など患部に触れても痛くない口当たりの良いものを食べましょう。
・ビタミンが多く含まれる食品は、生のまま食べるか汁ごと食べられる調理法にする
→タミンB群は水に溶けやすい性質があるためです。なるべく生のまま食べることや、汁物や煮物の味付けを薄味にすることを心掛け、汁ごと栄養を摂るようにしましょう。
・熱い食べ物は避ける
熱が口内炎を刺激してしまうため、熱い食べ物は避け人肌程度まで冷ましてから食べるようにしましょう。
・炭酸飲料や、アルコールは控える
炭酸飲料は炭酸の刺激が口内炎を悪化させる可能性があります。
アルコールは同様に口内炎を刺激してしまうだけでなく、分解する際に大量のビタミンを消費します。
・糖質の多い食べ物を食べすぎない。
ごはんやパン、ラーメンなど糖質の多い主食や、ケーキや菓子類などの甘い食べ物は、糖を分解するときにビタミンB群を消費してしまうため、食べ過ぎに注意する必要があります。
食べる時は栄養バランスを考え、ビタミン類と合わせて食べるようにしましょう。
・刺激の強い香辛料や、濃い味付けのものは控える
香辛料や濃い味付けの食べ物は、口内炎を刺激して痛みを増す原因となってしまいます。味付けは出汁を効かせて薄味にし、塩味や酸味、甘味は控えましょう。
・煎餅やフランスパン、いかやたこなどの硬く弾力のある食品は控える
硬い食品は患部を刺激してしまいますし、噛む回数が増えることで口の中を噛んでしまうおそれがあります。
・痛みが強く食べられないときは、栄養補助食品を利用する
一回に食べる量を減らしてみてもどうしても痛みで食事を食べられないときは、栄養補助食品を利用することでエネルギー量や栄養素を補うことができます。
栄養補助食品にはペースト状のものやゼリー、ドリンクなどがあり、痛みの程度に合わせ摂取しやすい形態を選びましょう。
なかなか口内炎が治らない原因は?
口内炎と見分けがつきにくい病気に、口腔カンジダ症やベーチェット病、口腔がんなどがあります。
これらは放置していても自然に治るものではありません。気になった場合は自分で鏡を見ながら口の中を観察してみましょう。
口の中の病気は主に歯科口腔外科と耳鼻咽喉科が専門の診療科です。
○口内炎が2週間以上経過しても治らない。
○舌の粘膜がただれや赤い斑点がある。
○口の中に白い斑点があるが痛みがない。
○口内炎とその周辺の境界線が曖昧であり、しこりや腫れがある。
このような症状がみられる場合は受診するようにしましょう。
・口腔カンジダ症
口腔カンジダ症はカビの一種であるカンジダ菌が口の中に感染することで発症します。
カンジダ菌は常在菌といってほとんどの人が保有している菌ですが、通常であれば発症することはあまりありません。
しかし。がんや糖尿病、加齢、ステロイド薬の影響など免疫力が低下した状態になると発症しやすくなります。
発症すると口内炎のような腫れや痛みだけでなく、口の粘膜や舌の表面に白い苔状のものが付着することがあります。治療には抗真菌薬のうがいが必要です。
・ベーチェット病
ベーチェット病は自己の免疫が異常に活性化することにより自分自身を攻撃してしまい、炎症をきたす疾患です。
なぜ自己の免疫が異常に活性化するのかについては、未だ分かっておらず、難病に指定されています。
症状は口内炎、皮膚や陰部の発疹、潰瘍、目のかすみや視力低下などで、消化管の潰瘍や関節炎を伴うこともあります。
多くの場合、はじめに口内炎がみられます。ベーチェット病は症状の再燃と寛解を繰り返す病気です。
現在のところベーチェット病を完治させることができる治療法はありません。
しかし、薬によって症状を和らげ、日常生活への影響を小さくすることができるようになっています。
・口腔がん
口の中にできるがんを総称して口腔がんといいます。口腔がんは全がんのうちの1%程度の珍しいがんです。
口の中の粘膜だけでなく、舌の両縁や裏、歯ぐき、上あごにがんができることもあります。発症初期は口内炎と見た目が似ています。
しかし、口腔がんの場合は口内炎のように自然に治癒することはなく、進行するにつれて症状が悪化していきます。
治療は、手術でがんを取り除き、必要に応じて放射線療法や抗がん剤治療を併せて行います。
口内炎がある時におすすめのレシピ
口内炎があっても痛みがすくなく、かつ口内炎の直りが良くなると言われている食べ物を使ったレシピを紹介します。
熱いまま食べると口内炎を刺激してしまうため、冷ましてから食べましょう。
☆サバ雑炊
【材料】
・ごはん 茶碗2杯
・サバの水煮缶 1個
・ネギ 1/2本
・水 400cc
・和風だしの素 小さじ1
・味噌 大さじ1
・鰹節 適量
①水を鍋に入れ、沸騰したらみじん切りにしたネギ、ほぐしたサバ(缶の汁ごと)、ごはんを入れて煮る。
②ひと煮立ちしたら弱火にしてだしの素と葱を入れる。
③ごはんが柔らかくなったら完成。器に盛り、鰹節を適量かける。
サバにはビタミンB2、B6が含まれており、これらは粘膜強化に相乗効果があります。
サバ缶を使うことで簡単に作れるだけでなく、水煮の汁の中にはDHAやEPAなどといった多くの栄養素が凝縮されているため一石二鳥です。
☆スフレ納豆チーズオムレツ
【材料】
・納豆 1パック
・たまご 1個
・マヨネーズ 小さじ1
・塩 ひとつまみ
・オリーブオイル 大さじ1
・スライスチーズ 1枚
①納豆とたまごの黄身、マヨネーズを混ぜ合わせる。
②ボウルに白身と塩を入れ、ツノが立つまで混ぜ合わせてメレンゲを作る。
③メレンゲと納豆をさっくり混ぜ合わせる。
④オリーブオイルをひいて熱したフライパンを中火にし、③を入れ、スライスチーズをのせる。
⑤蓋をして約2分焼き、裏が焼けたら半分に折りたたむ。
⑥器に盛って完成。
納豆とたまごはビタミンB群が豊富です。メレンゲを作るのが手間ですが、ふわふわで口溶けの良いオムレツを作ることができます。
加熱することでたまごに含まれるアビジンが納豆のビオチンの吸収を阻害しなくなるというメリットがあります。
☆バナナミルクセーキ
【材料】
・バナナ 1本
・たまご 1個
・牛乳100ml
①バナナを一口大に切り、材料を全てミキサーにかけます。
②グラスにうつして完成。
バナナにはビタミンB6、牛乳にはビタミンB2、そして栄養の宝庫であるたまご、と口内炎の時に積極的に摂りたい栄養素が含まれたミルクセーキです。
口内炎が痛くて固形物が食べられない時でも栄養を補給することができます。
口内炎についてのまとめ
口内炎は栄養不足や生活習慣の乱れ、ストレスなど様々な原因で起こります。
口内炎がある時の食事は、患部を刺激しないものを食べられる時に食べるようにしましょう。
口内炎の症状の感じ方には個人差があり、痛みの程度に合わせて食材や調味料、調理方法を工夫する必要があります。
また、口内炎は通常2週間程度で自然に治癒しますが、なかなか治らない場合や、再発を繰り返す場合には他の病気が隠れている場合があるため、歯科口腔外科を受診してみましょう。
口内炎の治癒の促進や予防のためには、栄養バランスの良い食事を摂って免疫力を高めることが大切です。
「栄養バランスの良い食事を毎日作るのは大変」という方は配食サービスを利用してみてはいかがでしょうか。
配食サービスを利用することで、手軽に栄養バランスの良い食事を食べることができます。
「まごころ弁当」では前日までのご注文で、自宅に栄養士が献立を考えたお弁当を届けます。
安心安全な食材を使い旬のものを取り入れた飽きの来ないメニューでありながら、手頃なお値段であることが魅力です。
一般の高齢者に向けたお弁当だけではなく食事制限がある方への対応や、摂食機能によって食事の形態を変更するなど、一人ひとりの事情に合わせて届けてもらうことも可能です。
この機会に是非無料試食サービスをお試しください。
 まごころ弁当
まごころ弁当  配食のふれ愛
配食のふれ愛  宅食ライフ
宅食ライフ  すくすく弁当
すくすく弁当  まごころケア食
まごころケア食  ライフミール
ライフミール  わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん  運営会社
運営会社  こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ