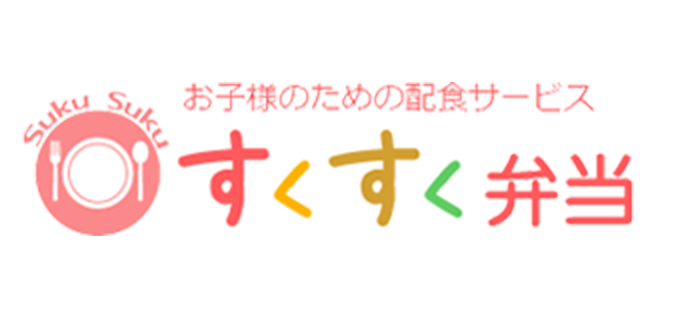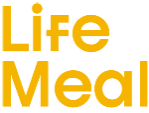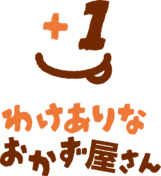こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!
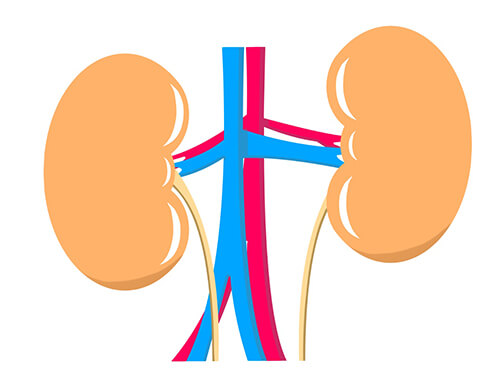
ひと昔前であればそれほど多くなかった腎臓病。最近の調査では成人の8人に1人が慢性腎臓病(CKD)だとも言われています。
慢性腎臓病は、他の病気と同じく早めの治療や対処が重要ですし、病気を進行させない工夫も大切です。
そこで今回は、腎臓病の基礎知識をお伝えしながら、腎臓病の治療や対処に欠かすことができない食事で使う「食材」「料理」のことについてもご紹介します。
目次
腎臓病とは?原因と種類
はじめに、普段私たちが胃や腸、心臓、肺などのように、気にすることが多くない腎臓について、そして腎臓病について見ていきましょう。
腎臓の働きを知ろう
腎臓の働きを正しく理解している方は、ともすると医療関係者くらいかもしれません。腎臓とは身体を健康に保つために静かに働いてくれている臓器です。
腎臓の代表的な役割は以下の5つがあります。
(1)老廃物を尿として排出する
血液中の老廃物や有害物質は、放っておくと体内へ溜まり続けます。それでは健康な体を維持することができません。
そこで腎臓は、老廃物や有毒物質を糸球体という組織で濾しとって除去し、尿として体外へ排出してくれています。
(2)体内の水分量を調整する
体の中には、それぞれ相応の量の水分が必要です。多すぎても少なすぎても私たちの体は健康な状態を維持することができません。
健康で一般的な成人の体内に含まれる水分量は、体重の約60%だと言われています。
腎臓は、必要に応じて尿として排泄する量を調整し、体内に必要な水分量を一定に保ってくれているのです。
筋肉の収縮などにも関わっている
私たちが手足を動かして行動するため、内臓を動かして呼吸や消化吸収活動を行うために、常に筋肉が働いています。
筋肉は脳から出た信号を受け取ると、電解質を利用して体を動かしています。
こういった活動を順調に行うためには、体内の電解質のバランスも大切なポイントになってきます。
この電解質のバランス調整も、腎臓の重要な働きの一つなのです。
(1)血圧の調整
多くの毛細血管が集まり、血液のろ過を行っている腎臓では、血圧の調整や赤血球を作る作用を促すために次のようなホルモンが作り出されています。
・エリスロポエチン
エリスロポエチンは、骨髄が血液を作る作用を促す働きがあります。
・レニン
レニンは腎臓のろ過装置、糸球体で作られ、血管の収縮を調整して血圧を一定に保つ働きを促しています。
・キニン
キニンは血管の収縮を調整し、血圧を一定に保つ働きがあります。
こういったホルモンがバランスよく作られないと、季節や温度にあわせた血圧を維持し、健康で快適な日々を過ごすのは難しくなってしまいます。
(2)骨の強化
骨を強化するためには、ビタミンDが必要です。腎臓はビタミンDの活性化も行っています。
腎臓は他の臓器とは違い、普段はあまり気にすることがないと思います。
胃や腸のように痛みを感じることも少ないですから、知っていないと何もわからない臓器のままという方もいらっしゃることでしょう。
しかし、今ご紹介したように血圧の安定や体内水分量の調整、また、骨の健康維持など、とても大切な役割を担っています。
腎臓病はどんな病気?
腎臓病とは、腎臓の中にある「糸球体(しきゅうたい)」や「尿細管」が破損することで、その働きが低下する状態です。
その結果、
・老廃物が尿として排出されにくくなる。
・体内の水分量の調整や電解質のバランスが崩れてくる。
・血圧を調整するホルモンなどが作られにくくなる。
・骨を強くするビタミンDの活性化ができにくくなる。
などの症状がみられるようになります。このようなことが引き起こされるため、外から見た体はいつもと何ら変わりないようであっても、内側では少しずつ無理を強いられていることがあります。
腎臓病には2つの種類がある
腎臓病には、次の2つの種類があります。
(1)急性腎臓病
次のような腎臓病を患うことで感じる症状や、腎臓が行う働きの低下を短期間で経験します。
・急に尿の出が悪くなる。
・体がむくみやすい。
急激な体調の変化を経験する分、早い段階で病気を発見し、治療に結びつくことが多い状態です。
また、適切な治療を行うことで回復することも可能だと言われています。
多くの場合、急性腎臓病は、急性糸球体腎炎やケガによる一時的な腎臓機能の低下が原因と言われています。
(2)慢性腎臓病
こちらは徐々に、静かに腎臓病が進行する状態です。腎臓病が進行していても自覚症状がほとんどないという点が問題です。
少しずつ進行するので気に留めることもなく、病院に治療へ行く方も多くないのが現状だと思います。
しかし、慢性腎臓病で症状を感じ始めたときはかなり進行していますので、一時的な入院などが必要になることもあります。
また、糖尿病などを併発する可能性も高くなるため、思っている以上に重症化していたり、複数の病気を治療しなくてはいけなかったりすることもあります。
国民病ともいえる腎臓病
慢性腎臓病(CKD)の患者数は、推測で180万人を超えていると言われています。
自覚症状が出にくい腎臓病は、発症していることにも気づかずに治療していない人が多く、患者数の実態をつかみにくい病気の一つです。
しかし、ここで注目することは、慢性腎臓病の疑いのある患者が増えていることでしょう。
これは糖尿病と同じように「国民病」と呼んでもおかしくない状態だと言えます。
腎臓病は予防が重要ですし、健康診断などを通して数値の異常が見られた場合には、病院で検査や治療を行うようにすることが大切です。
腎臓病は治療せずに放っておくと「いつの間にか完治していた」ということがない病気です。
進行することはあっても完治することはありません。
そして、腎臓病を放っておくと、
・腎不全
・心筋梗塞
・心不全
・脳卒中
などを引き起こす原因にもなると言われています。
いつまでも健康な体を維持するためには、静かな臓器のメッセージを受け流すのではなく、しっかりと受け取って検査をしてみることが大切です。
腎臓病の症状とステージ
腎臓病の症状と経過について少し見ておきましょう。もしかすると、あなたもこれからお話するステージの中にいるかもしれません。
6つのステージ
腎臓病は腎臓の機能状態によって下のようにステージが決まります。
CKDの重症度分類(CKD診療ガイド2012)
| 原疾患 | ステージ | 蛋白尿区分 | |
| GFR区分(ml/分/1.73m2) | G1 | 正常または高値 | >=90 |
| G2 | 正常または軽度低下 | 60~89 | |
| G3a | 軽度~中等度低下 | 45~59 | |
| G3b | 中等度~高度低下 | 30~44 | |
| G4 | 高度低下 | 15~29 | |
| G5 | 末期腎不全 | <15 | |
出典:日本腎臓学会-エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018より抜粋
URL:https://cdn.jsn.or.jp/data/CKD2018.pdf
G2までであれば、生活改善や適切な治療によって回復する可能性が高くなります。
G3以上になると、治療によって悪化を防ぐことはできますが、完全に回復することは難しいと言われています。
このようなステージを見ると、腎臓病は早期発見から早期の治療、そして生活改善が重要なことがわかります。
症状について見ていきましょう
先ほども少しふれましたが慢性腎臓病の場合、初期は自覚症状がほとんどありません。
ステージがG1になったときでも、尿から蛋白が少し多めに排出される程度なので、自覚症状はほとんどないでしょう。そして腎臓の機能も正常に働いています。
ステージG2になると、腎機能の低下が認められます。とはいえ、認められるのは健康診断などで検査したときです。まだ、このステージでは自覚症状はありません。
ステージG3に入ると腎臓の機能低下が進み
・尿に蛋白が多く含まれる
・血尿が出る
・むくみやすくなる
・血圧が上昇しやすい
・尿の量が増える
という症状が感じられます。ここで「おかしいな」と感じられ診察を受けられた場合は、早期に悪化を防ぐことができるでしょう。
ステージG4に入ると、腎不全を起こしていることがあります。体内の老廃物などが尿と一緒に排出されにくくなっているため、
・だるさ
・吐き気
・食欲不振
・頭痛
・呼吸困難
・貧血
このような症状を感じる方も出てきます。
G4ステージの場合は、これまでの健康診断で数値異常を指摘されているはずです。速やかに診察されることが必要です。
ステージG5になると腎不全を起こしていますので、専門医の治療が必要になるでしょう。
このように腎臓病は、放っておくとステージがどんどんと進行します。そしてステージが進行する度に、回復しづらくなっていきます。
適切な治療と生活改善によって腎機能を助けることを意識しておきましょう。
腎臓病の治療に必要なこと
腎臓病の治療には、次からお話しする方法が必要になってきます。
腎臓病はお薬だけで治療できるものではありません。私たちが治療で意識しておきたいことは、腎臓の働きを助けるようにすることです。
お薬
腎臓病は自然に治癒することはないと言われています。ですから、腎臓の機能を助けるために、お薬の服用は必要になってきます。
かかりつけの医師から処方された、あなたの症状やステージに必要なお薬をきちんと服用するようにしましょう。
食事
腎臓病はお薬を使った治療と平行して、これ以上症状を悪化させないために食事にも気をつけることが大切です。
食塩や、タンパク質、リンやカリウムなどの制限も必要になってきます。
生活
肥満の改善や予防のためには、無理のない程度に体を動かすことも必要になってきます。
また、ストレス、長時間労働などを避ける工夫。疲れを溜めないように心掛けた生活改善も重要です。
合併症予防
腎臓病で気をつけておきたいのは合併症です。
体の中に溜まる不要な物質を排出しにくくなっていますから、他の病気を引き寄せやすくなってしまいます。
また、間違った食事制限をすることで、栄養不足が起こることもありますので、体力、免疫力が落ち、風邪やインフルエンザなどから別の病気を引き起こす可能性もゼロではありません。
腎臓病の方におすすめの食事~食事療法が大切な理由~

それでは毎日の暮らしのなかで必要な、「食事療法」について見ていきましょう。
食事療法の目的
どうして食事療法を行うのか。
その理由とは
・腎臓病の進行を遅らせること
・体調を良好に維持すること
この2つが大きな目的となります。
また、腎臓は常に働いてくれていますので、適切な食事療法をすることによって、腎臓の負担を軽くすることも目的の一つだといえます。
食事療法のポイント
腎臓病での食事療法には3つのポイントがあります。
(1)食塩の制限
食塩のとりすぎは、水や塩分のバランスを取ることを難しくします。
腎臓の働きを軽くするためにも、かかりつけの医師や管理栄養士の指導をうけ、とってもよい塩分量を把握しておきましょう。
むくみや高血圧を引き起こしにくくするためにも、食塩の制限は大切なポイントとなります。
塩分の取り過ぎを予防するためにただ薄味で調理をすると、物足りなさから食べるときに塩やしょうゆを足してしまい、かえって逆効果になることがあります。
調理の際には、和食なら大葉やしょうが、三つ葉、ゆず、洋風ならバジルやパセリなど、香りのよい野菜やスパイス、酢などをプラスして、味や香りの幅を持たせると、塩分の物足りなさをカバーすることができます。
減塩を成功させるには、以下のようなポイントもあります。
・調味料はきちんと計って計算する
ついつい使いすぎてしまいますので、きちんと計量し、数字で判断しましょう。
・質の良い調味料を使いましょう
質の良い調味料はうまみ成分が多いため、少量でもおいしく食べられます。
市販の出汁を利用する場合はパッケージの表示を確認し、無塩や減塩と表示されているものを選ぶようにしましょう。
加工品は回数を減らそう
加工食品はどうしても塩分が高めになりやすいです。極力、食べる回数を減らせるよう、作り置きなどを活用しましょう。
外出などでどうしても避けられない外食は、麺類は汁を残す、添付のつけだれやドレッシングなどは極力使わないようにするなどすると、減塩につながります。
(2)エネルギーの摂取
食事療法で「制限がある」と聞くと、何でも制限しなくてはいけないように感じる方もいらっしゃいます。
しかし、私たちの体には適切なエネルギーがないと、活動することも内臓を動かす力も出てきません。
適切なエネルギー摂取は大切なポイントです。かかりつけの医師や管理栄養士の指導をうけ、適量をとりましょう。
ビタミンB群は脂質やたんぱく質、糖質をエネルギーに変換する働きがあります。
食べられる食材から、これらを多く含む食品を使ったメニューを増やすとよいですね。
(3)タンパク質の制限
タンパク質が少なすぎると、筋肉や内臓、血液、免疫細胞などを作ることができなくなります
。しかし多すぎると腎臓に負担がかかりますので良くありません。
難しいところではあるのですが、タンパク質は腎臓の負担にならない程度に摂取することが大切なのです。
たんぱく質の摂取量についても、かかりつけの医師や管理栄養士の指導をうけておきましょう。
後ほどご紹介する『腎臓病食交換表』などを活用し、どの食品をどの程度食べても良いのかを、目分量でも覚えておくと、外食時に判断する目安になりますよ。
控えたい3つの栄養素
症状によっては、次の3つの栄養素の制限が必要になる方もいらっしゃるでしょう。
・カリウム
・リン
・水分
どれも私たちの体にはとても大切で、なくてはならない栄養素です。
しかし、腎臓病を患ってしまった場合、体に負担がかかる栄養素でもあります。
取り過ぎず不足せず、適量を取ることが大切です。
かかりつけの医師や管理栄養士に、どのような食品に上の3つの栄養素が多く含まれているのかを教わり、よく口にする食材は特に注意しておくことが必要です。
食材別栄養価リスト
ここでは、普段の生活で食べることが多い食材について見ておきましょう。
| エネルギー | タンパク質 | 水分 | カリウム | リン | 食塩相当量 | ||
| 玄米 | 1膳150g | 228kcal | 4.2g | 90.0gg | 140mg | 200mg | 0g |
| 精白米 | 膳150g | 234kcal | 3.8g | 90.0g | 44mg | 51mg | 0g |
| 切り餅 | 1個50g | 112kcal | 2.0g | 22.3g | 16mg | 11mg | 0g |
| オートミール | 6g | 21kcal | 0.8g | 0.6g | 16mg | 22mg | 0g |
| 食パン | 6枚切り1枚60g | 148kcal | 7.8g | 39.2g | 76mg | 51mg | 1.3g |
| バターロール | 小1個30g | 93kcal | 3.0g | 9.2g | 33mg | 29mg | 0.4g |
| クロワッサン | 1個40g | 162kcal | 6.5g | 20g | 110mg | 65mg | 1.3g |
| うどん(ゆで) | 1玉240g | 228kcal | 6.2g | 180.0g | 22mg | 43mg | 0.7g |
| そば(ゆで) | 1玉170g | 221kcal | 8.2g | 115.6g | 58mg | 140mg | 0g |
| 牛バラ(和牛・脂身付き) | 100g | 472kcal | 11.0g | 38.4g | 160mg | 87mg | 0.1g |
| 豚肉もも(脂身なし) | 100g | 153kcal | 21.3g | 69.6g | 360mg | 200mg | 0.1g |
| 鶏もも(若鶏皮つき) | 100g | 190kcal | 16.6g | 68.5g | 290mg | 170mg | 0.2g |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)より
URL:https://fooddb.mext.go.jp/
このように一つひとつの食材を見ると、塩分は少ないですね。
卵や牛乳、ヨーグルトについても同様で、それぞれ、良質のたんぱく質やカルシウムを含んでいます。
野菜類は、私たちの体を維持していくために必要なビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含んでいます。
どの食材が腎臓に良くてどの食材が腎臓に悪い、ということも確かに重要です。
しかし、それよりも大切なことは食材そのものと同様に調理方法に気を配るということです。
揚げ物がどうしても食べたい場合は、天ぷらやフライよりも素揚げ、唐揚げを選びましょう。
塩分や脂を含む衣が少なくカロリーを少しでも抑えることができます。
炒め物は、塩分を多く含むタレがフライパンの底に溜まった場合、盛り付けの時にフライパンを斜めにかたむけ、溜まったタレを落としてから盛り付けるなど、日々のちょっとした工夫で減塩メニューを楽しむことができますよ。
『腎臓病食交換表』を活用する
腎臓病の食事について指導を受けた際に、『腎臓病食品交換表』という本を勧められると思います。
この本の中には、どのような食材がどの程度食べられるかや、例えばタイを150g使う料理を作りたかったのに、サワラしか手に入らなかった場合、サワラなら何g食べることができるかを知ることができます。
腎臓病の栄養指導について、かかりつけの医師や管理栄養士の指導を受けた時、その時の病状に合わせた単位を指示されますね。
単位というとなかなか分りづらくとっつきにくく感じるかもしれませんが、この『腎臓病食交換表』では食品が重量と合わせて単位づけされています。
一日に食べられる単位数を大まかにでも覚えておくと、食材選びやメニュー選びにも役立ちますよ。
中にはたくさんのレシピが朝食、昼食、夕食向けに分けて掲載され、それぞれを組み合わせることで理想のメニューを作ることができるようになっているものもあります。
パズルのように食品をあてはめ、上手に活用してみてくださいね。
外食をするときの注意点
例えば鶏肉なら、あっさりとした蒸し鶏とは違い、しっかりとした味付けの唐揚げには、おおむね多くの塩分がふくまれています。
豚の生姜焼きなども調味液の生姜には、塩分はそう多くありません。しかししっかりと濃い味付けにするため、しょうゆなどで塩分を多く入れているところもあるでしょう。
カレーも同じです。スパイスの辛さなら塩分は少ないですが、濃い味付けにするために塩を含む調味料を多く加え、1食で6gを簡単に超えていることもあります。
外食をするときには、食材を選ぶことも大切ですが、選んだメニューが
・濃い味付けだな
・塩分が強いな
・量が多いな
と感じられた場合には、残す勇気をもちましょう。
日本人は「もったいない」の文化を持っています。食事を残すことに罪悪感を持つ方が多いですが、健康維持のためには残すことも必要です。
いつも行くお店であれば、最初から「少なめ」をオーダーする、つけダレやドレッシングなどは量を減らすか使わない、など、少し工夫することで、食事療法をスムーズに進めることができるでしょう。
はじめは物足りなく感じるでしょうが、徐々に慣れていくことと思います。
食材選びとあわせて、料理の方法、味付け、食べる量を総合的に考えていただくことが、腎臓への負担も、あなたへのストレスも軽減できる方法だと思います。
腎臓病の人に良い食事まとめ
腎臓病の疑いがある方や、通院、治療中の方には、今回お伝えしましたような栄養素を意識しながら、良い食材を選び、食事療法をスムーズに進めていただきたいと思います。
しかし、こういった食事制限考え、料理を毎日作るのは大変なものです。
そこでオススメなのが、栄養バランスと制限を守った食事を簡単に食べられる「配食サービス」の利用です。
わたしたち、配食のふれ愛では、原材料からこだわった食材と栄養バランスを考えたお弁当が、ご注文いただくだけであなたのお家に届きます。
週に2回くらいのご利用から検討いただくと、毎日の家事も少しは楽になるかと思います。
今なら無料試食キャンペーン中ですので、お気軽に試していただけると幸いです。
 まごころ弁当
まごころ弁当 配食のふれ愛
配食のふれ愛 宅食ライフ
宅食ライフ すくすく弁当
すくすく弁当 まごころケア食
まごころケア食 ライフミール
ライフミール わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん 運営会社
運営会社 こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 配食のふれ愛とは
配食のふれ愛とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ